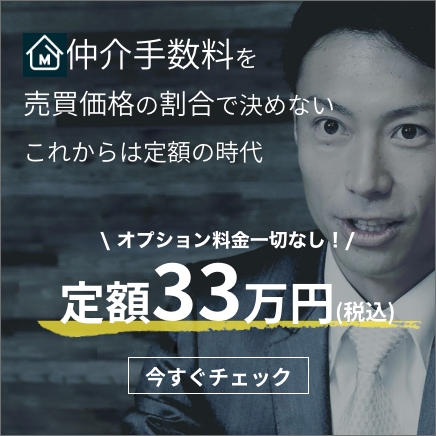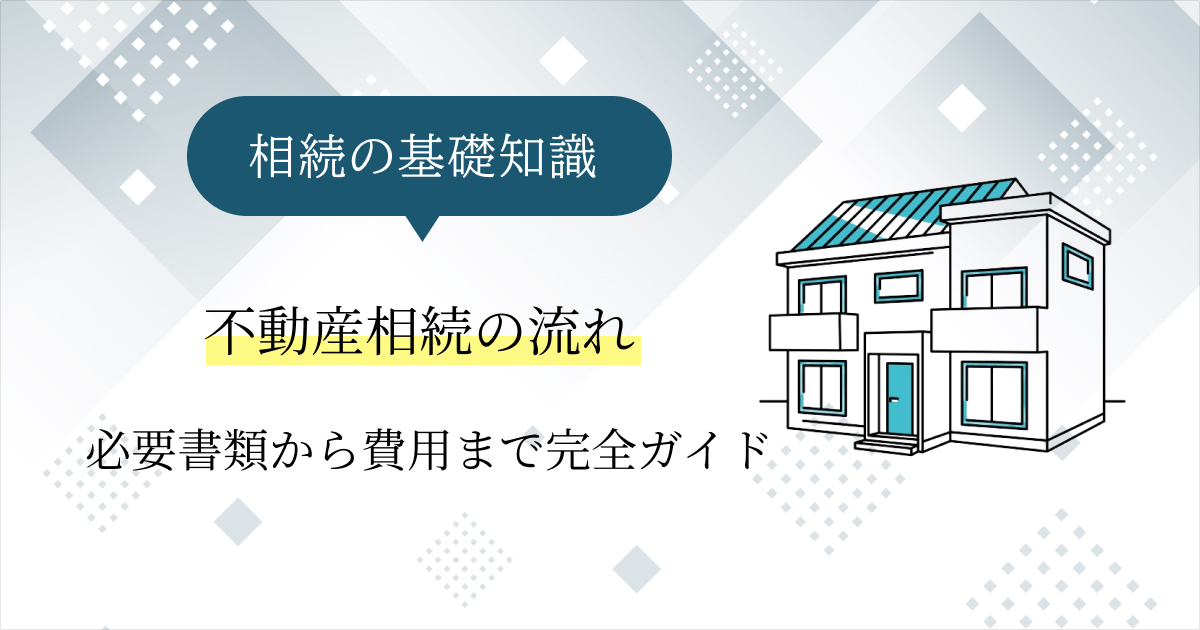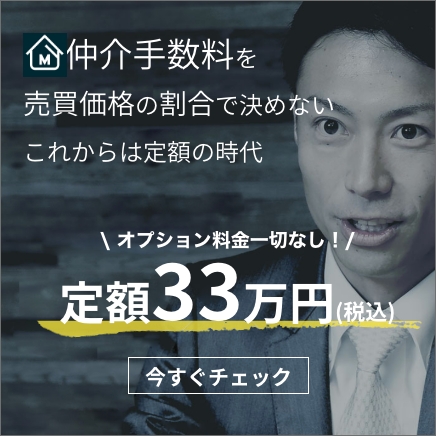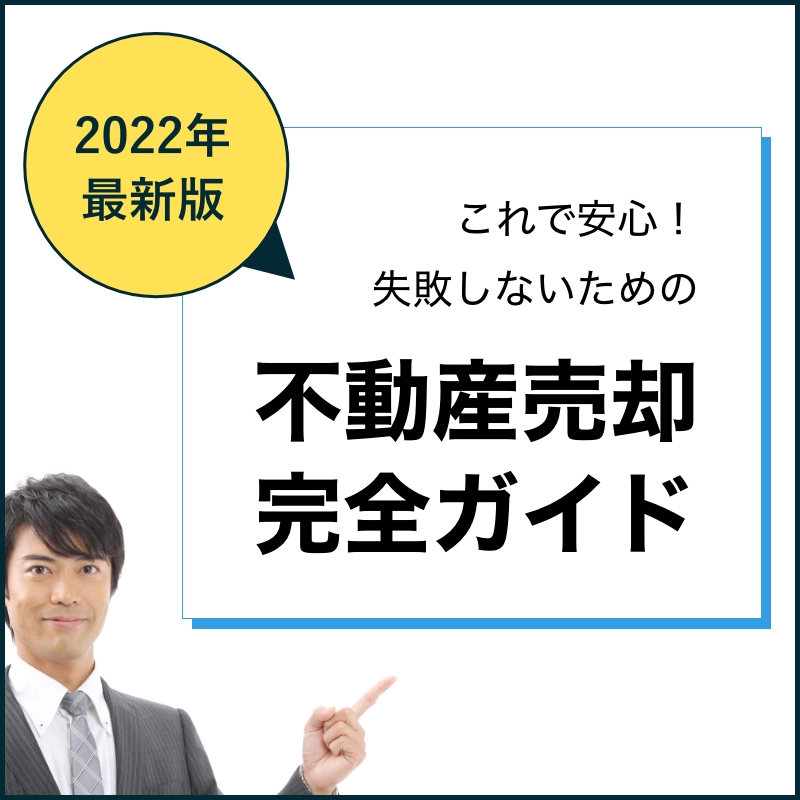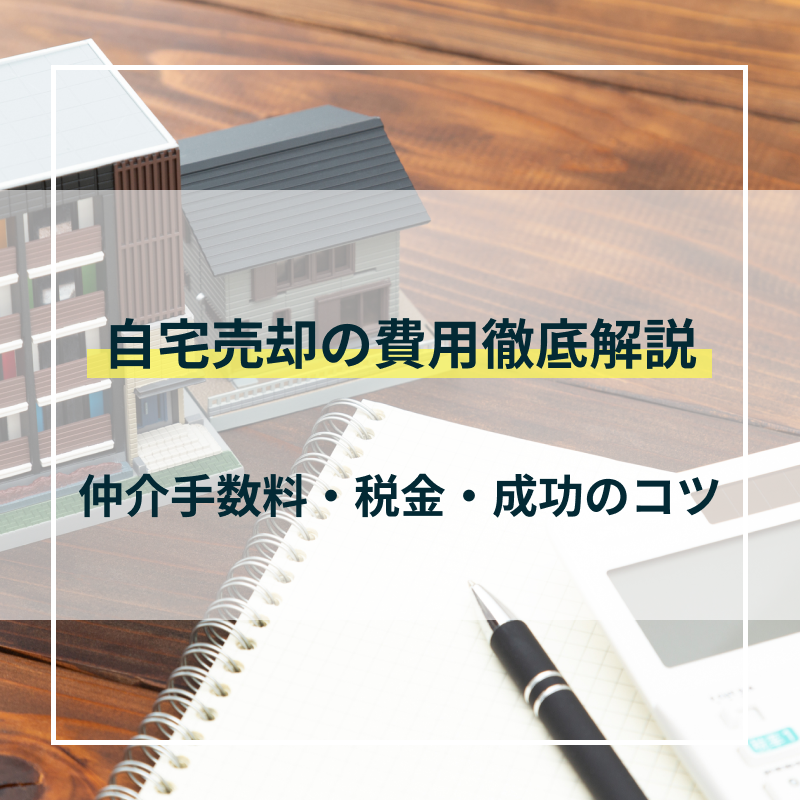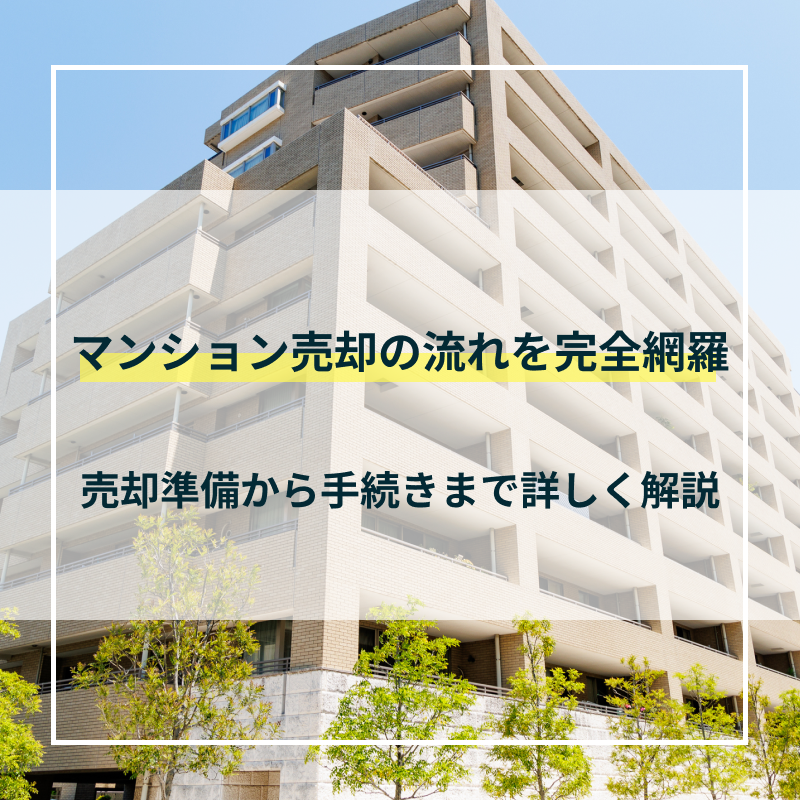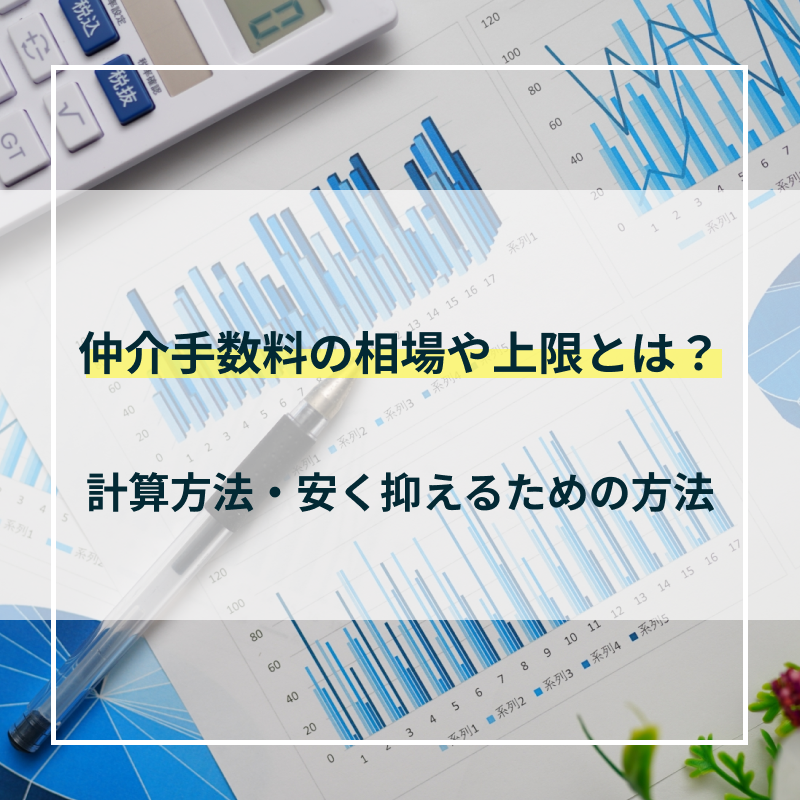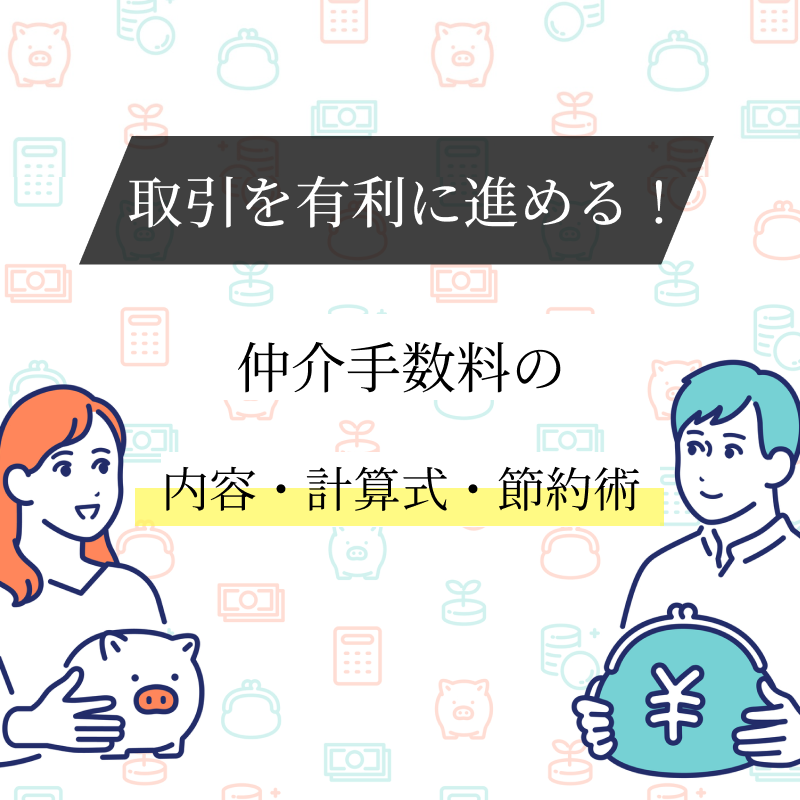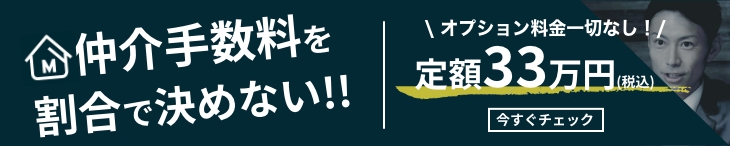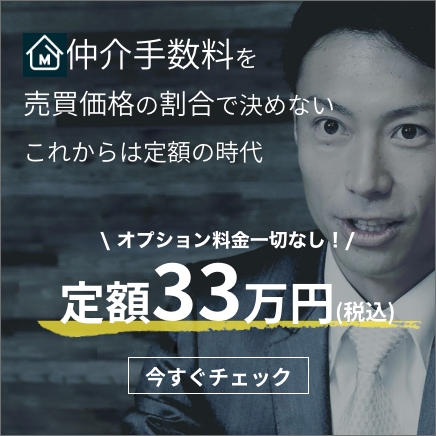
不動産の相続は突然発生するケースが多く、税金や手続きについて分からないと悩まれる方も多いでしょう。
この記事では、相続の基本的な情報と、不動産を相続する流れや方法、必要書類、費用などを詳しく解説します。
この記事を最後まで読めば、不動産を相続する際に知っておくべき基礎知識や、節税対策についても理解でき、相続にまつわる不安や疑問が解消されます。
相続の基礎知識
民法典という法律では、人が死亡すると相続が開始する、と決められていて、誰がどの割合で遺産をもらうことができるのか(「法定相続分」)が規定されています。
法定相続人は原則的に配偶者と子供
法定相続人は、原則的に配偶者と子供で、「配偶者が2分の1、子供が2分の1」の割合で取得します。
配偶者は1人しかいませんから生存していれば必ず2分の1を取得する権利がありますが、子供が3人いる場合、2分の1×3分の1で子供1人の相続分は、6分の1です。
配偶者がいるものの、子供がいない場合、生存している配偶者と亡くなられた方の親が相続し、相続分の割合は「配偶者が3分の2、親が3分の1」です。
親が両方とも亡くなっていれば次に祖父母の代になりますが、こうなると多くの場合、すでに他界されており、上の世代には生存者がいないことになります。
そうなりますと、次に他界された方の兄弟姉妹にいき、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹の相続分は「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」の割合で取得することになります。
法定相続の割合を変更するための「遺産分割協議」
法定相続人の相続割合はありますが、実際は相続分の割合は、話し合いで相続する人を法定相続分ではない割合に変更して取得するというケースの方が一般的です。
例えば、お父さんが亡くなってお母さんと子供2人がいる場合に、子供2人はすでに独立しており、お父さん名義の不動産に現在お母さんしか住んでいない、またほかには特に分配する遺産もないというような場合には、不動産名義をお母さんだけの名義にする方がよい、ということもあるかと思います。
そのような場合には、相続人3人で話し合って、「お父さんの遺した不動産は、お母さんが1人でもらうことにしましょうよ」と決められます。
これを「遺産分割協議」といいます。
不動産を相続する流れ
まず、相続が発生した時の流れを期限に注目して確認しましょう。
相続の手続きは、「いつまでに」が決まっているものが多く、この期限を頭に入れ、計画を立てながら進める必要があります。
最初にやってくる期限は、「7日以内」と「14日以内」です。役所への届出等、事務手続きがほとんどです。
次にやってくるのは、「3か月」と「4か月以内」の期限で、相続の放棄や準確定申告といった事前準備が必要な手続きになります。
そして、相続税の申告期限が「10か月以内」、遺留分侵害額の請求期限が「1年以内」となります。
・死亡診断書を受け取る
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
・世帯主の変更届の提出
・国民年金、厚生年金の受給停止の手続き
・国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き
・相続放棄
・単純承認
・限定承認の決定
・準確定申告
・10か月以内
・相続税の申告
・遺留分侵害請額の請求
遺留分侵害額の請求とは、法定相続人が最低限取得できる、一定割合の相続財産を主張する権利です。
この権利を行使できるのは、被相続人の死亡日または相続開始を知った日から1年以内です。
次に、不動産を相続する手続きについて確認しましょう。
不動産を相続する手続きの流れは以下の通りです。
- 遺言書を確認する
- 相続人を確定する
- 財産を特定する
- 遺産分割協議を行う
- 不動産の相続登記を行う
- 相続税の申告し納税する
遺言書を確認する
不動産の所有者が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は基本的にその内容に従って相続手続きが進められるので、遺言書を早期に見つけることが重要です。
一方、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合う必要があります。
遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合でも、遺言書の内容が優先されるため、遺言書の確認が最優先です。
相続人を確定する
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の親族が相続人となるため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、正確に相続人を特定する必要があります。
相続人を確定させるためには、できるだけ早期に調査する必要があります。
もし新たな相続人が後から発覚した場合、一度決まった遺産分割協議をやり直さなければならなくなるため、相続人の特定は慎重かつ迅速に行う必要があるからです。
遺言書があれば、基本的にその内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いによって遺産の分け方を決めます。
財産を特定する
相続手続きを進めるためには、まず被相続人の財産を特定し、財産目録を作成することが重要です。
不動産については、被相続人が所有していた可能性がある市区町村で固定資産税の課税明細書を確認したり、役所で「名寄帳」の写しを取得すれば、所有不動産の情報を一覧で確認可能です。
課税明細書がない場合は、疑わしい市区町村の役所で「名寄帳」を調べる必要があります。
また、預貯金については通帳や残高証明書で確認し、不動産については固定資産税の納税通知書や権利証を確認するといった具合に、被相続人の財産を丁寧に特定していく必要があります。
財産の特定作業を行い財産目録を作成するのは、後の遺産分割協議がスムーズに進めやすくするために重要です。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が一人でも欠けた状態で行われた分割協議は無効となるからです。
協議の結果、不動産などの相続財産の分割方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・押印します。
遺言書がある場合は、原則としてその遺言書の内容に従って相続が行われます。
遺言書にせよ遺産分割協議書にせよ、相続財産の分割方法を明確に定めた文書を作成し、相続人全員の合意を得ることが重要なポイントです。
不動産の相続登記を行う
不動産の相続手続きは、不動産の所有者が相続人に変更するための相続登記が重要です。
相続登記とは、被相続人から相続人への不動産の名義変更の手続きのことです。
相続登記には、「不動産を相続するための必要書類」で後述する書類が必要となるため、事前に書類の準備をしておく必要があります。
相続税の申告し納税する
不動産を含む遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の支払い義務が生じます。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内で、この期限内に申告・納付しないと、様々な罰則が科される可能性があります。
無申告加算税や延滞税などが課される可能性があるため、必ず期限内の申告・納付しましょう。
複数の相続人で不動産を相続する方法
相続人が複数存在する場合不動産の相続は、現金のように均等に分割できないため、以下の4つの方法で相続します。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有名義
現物分割
「現物分割」とは、不動産を含む財産をそのままの形で相続する方法です。
例えば、相続人が2人いて不動産が2つある場合、各相続人が1つずつ相続するといった形態が該当します。
現物分割は手続きが簡単で分かりやすい一方で、相続財産の評価額に差がある場合、評価額の低い財産を相続した人から不満の声が上がる可能性があります。
現物分割は主に土地のみの相続に適しており、建物を含む不動産の場合や分割により価値が著しく低下するような場合には向いていない可能性があります。
代償分割
「代償分割」とは、特定の相続人が相続財産の一部を単独で取得し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
この方法では特定の相続人が不動産を引き継いで、他の相続人は現金を得られるため、相続人の意向に合わせて財産を分割できるというメリットがあります。
一方で、代償金の金額をめぐる争いが生じやすく、相続人が代償金を用意できない場合には代償分割できないという課題もあります。
換価分割
「換価分割」とは、相続財産である不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で均等に分割する方法です。
換価分割は、相続人全員が不動産の相続を望んでいない場合や、相続税の支払いに現金が必要な場合に有効な手段といえます。
ただし不動産の売却価格に左右されるため、希望通りの金額が相続できない可能性や、相続人全員に譲渡所得税がかかる点に注意が必要です。
共有名義
不動産の相続方法として、相続人が「共有名義」で相続する方法があり、各相続人の所有割合を持分割合として登記します。
共有名義で相続すると、将来的に不動産の売却や賃貸の際に、全ての共有名義者の同意が必要となります。そのため、意見の不一致や連絡が取れなくなるなど、トラブルが発生する可能性があります。
共有名義で相続すると、不動産の管理や処分が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
不動産を相続するための必要書類
相続登記を申請するのに必要な書類は、遺言書もしくは遺産分割協議書のほかに、以下のようなものがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のものだけ)
- 被相続人の戸籍の附票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
基本的に戸籍は、出生時に親の本籍地に入ります。
その後、結婚すると夫婦の戸籍を作成したり、別の本籍地に変更したり、また法律による改製があった場合に新しく戸籍が作成されます。
被相続人が出生したときのものから死亡するまでのものをすべてを集めることが重要です。
なぜ、それが必要かというと、すべての戸籍が揃わないと、その方の人生で相続人になるべき人が誰なのかを証明できないからです。
登記申請の場合は、生殖年齢である13歳程度からの戸籍がそろっていれば登記申請ができるのが基本ではありますが、銀行の相続手続きでは出生からのものを求められる点や13歳前後のものを取得できたならば多くの場合は出生時のものを取得するのは比較的容易なため、出生時のものから集めることをお勧めします。
相続人全員の戸籍謄本(現在のものだけ)
相続人が存命である証拠として、発行日が被相続人の死亡日以降の戸籍謄本が必要となります。
被相続人の戸籍の附票
登記簿上の住所が、Aという住所で登記されていたとします。
この場合に、被相続人とこの登記簿上の名義人が同一人物であることの法務局の判断基準は、「住所と氏名が一致すること」です。
なので、登記した後に住所を移転した場合には、今までの住所の変遷が記載された証明書を添付しなければなりません。
「戸籍の附票」とは、ある本籍地にいる間に住所を何回か移転しても、その住所の変遷が記載されている書類です。
「住民票の除票」というものもあるのですが、これは前住所しか記載されないため、例えば、登記簿上の住所がAでその後Bに住所を移転して、そのままBで死亡した場合には、住民票の除票を取得すれば、前住所の欄にAが記載されています。
これが、A→B→Cと移転し、Cで死亡した場合には、住民票の除票を取得しても、前住所に欄にはBしか載らないので、戸籍の附票を取得する必要があるのです。
「戸籍の附票」や「住民票の除票」は、基本的には死亡して5年経過すると廃棄処分されるため、5年以上経過してから相続登記する場合には、登記簿上の住所を証明する書類がもはや添付できないということになります。
この場合には、法務局の運用としては、役所に廃棄されたことを証明する「廃棄証明書」を発行してもらい、これと被相続人が登記した際の「登記済権利証」を添付することで、登記できるものとなっています。
【戸籍の附票】
「戸籍の附票」とは、ある本籍地にいる間に住所を何回か移転しても、その住所の変遷が記載されている書類です。
不動産を取得する相続人の住民票
相続登記にかぎらず、不動産登記では新しく名義人になる場合は、住民票を添付しなければなりません。
理論的には住民票を添付すれば、「架空の人物が名義人になる恐れはなくなるだろう」ということになっているからです。
不動産の登記事項証明書
土地・建物の登記事項証明書とは、法務局の登記簿に記録された土地や建物の所有者情報を記載したものです。
2008年に全国の登記簿の記録が電子データ化され、登記記録をダウンロードして印刷・認証したものを登記事項証明書として交付しています。
不動産の固定資産評価証明書
固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額が記載された証明書です。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村長等が決めます。
不動産の相続にかかる費用
不動産を相続すると以下のような費用が発生します。
- 相続税
- 登録免許税
- その他の費用
相続税
相続税は、被相続人から相続人へと財産が相続された場合に、その財産の総額に課される税金です。
相続財産には不動産、現金、有価証券、美術品などが含まれ、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合は、相続税が課されます。
相続税の基礎控除額は、3,000万円 + (法定相続人の人数 × 600万円)です。
つまり、遺産総額が3,600万円までは非課税ですが、3,600万円を超える場合は、超過分に応じて相続税が課税されます。
登録免許税
相続登記を行う際は、登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税の計算方法は、以下の通りです。
登録免許税=不動産の価格(課税額) × 0.4%
最終的な金額の下2桁を切り捨てた額が、最終的な登録免許税の金額となります。
その他の費用
相続登記には、以下のような費用が発生します。
- 登記事項証明書、戸籍謄本、住民票などの書類取得費用
- これらの書類を法務局に送付するための郵送費
- 登記事項証明書を法務局の窓口で交付請求する際の手数料(1件につき600円)
- 相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
相続登記には、不動産の価格に応じた登録免許税に加え、書類取得費用や送料、手数料などの各種費用が必要です。
相続登記を行う際は、これらの費用も見積もっておく必要があります。
オススメ記事
名義人が違う不動産を売りたい!土地と建物の名義が違う時の売却方法を5選!
そもそも不動産は、基本的には土地と建物の名義が異なると売却をすることができません。今回の記事では、どんな場合に名義人が異なってしまうのか、そうなった時に売却するための方法を詳しくご紹介していきます。
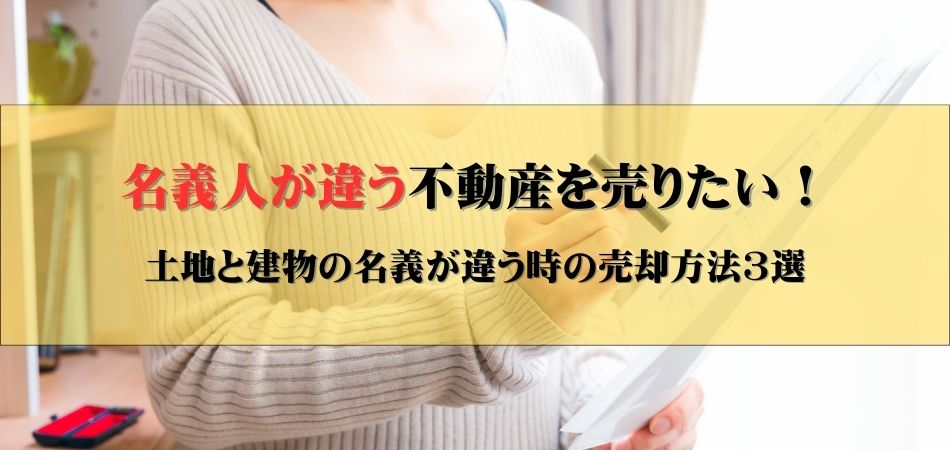
不動産の相続登記は専門家に相談しよう
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続登記を行わずに放置していると追徴課税される可能性があるため、相続が発生した際は、確実に相続登記を行うことが重要です。
相続手続きは複雑で煩雑なため、できる限り早い段階で実績と専門知識が多い仲介業者に相談することをおすすめします。
この記事が、不動産相続に関する知識を深める一助になっていたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。