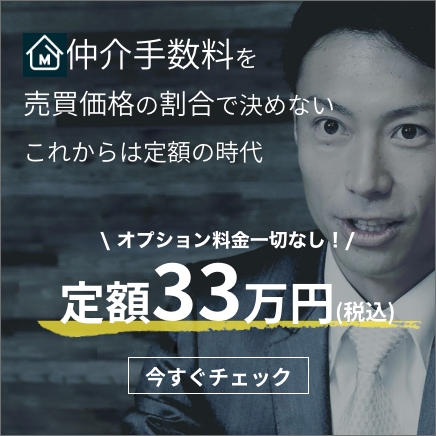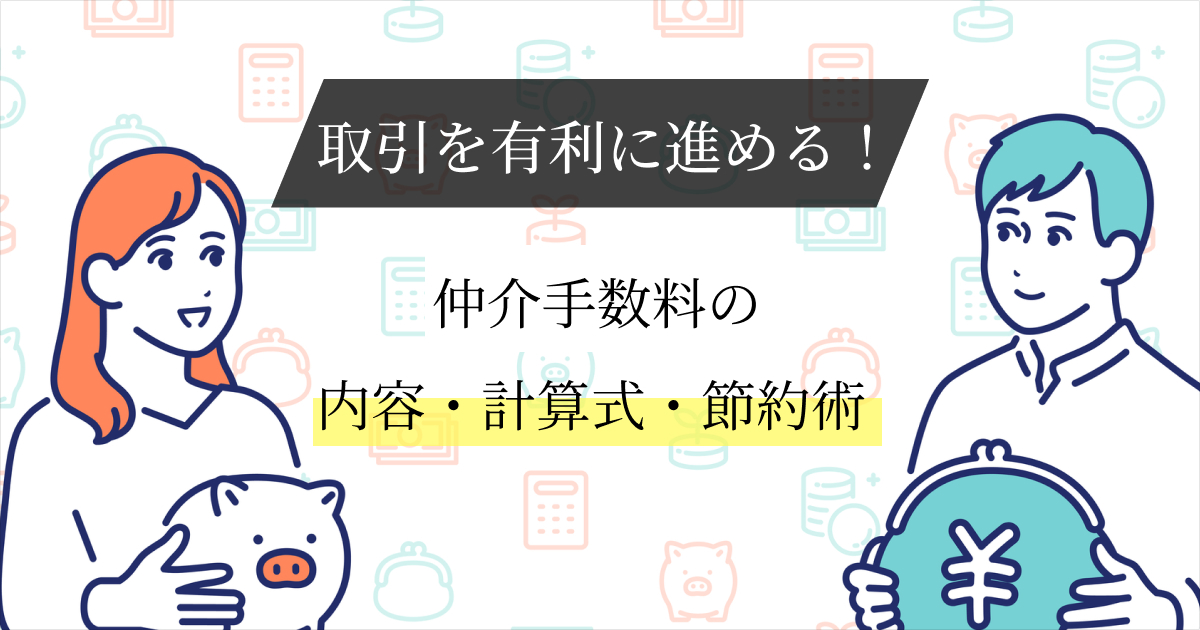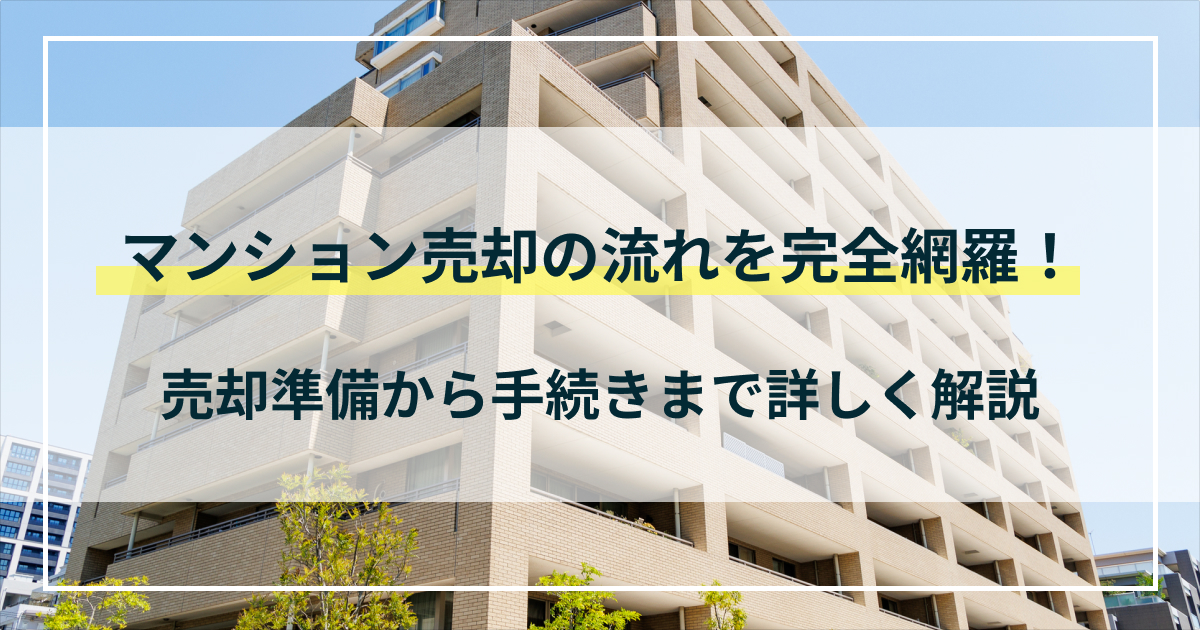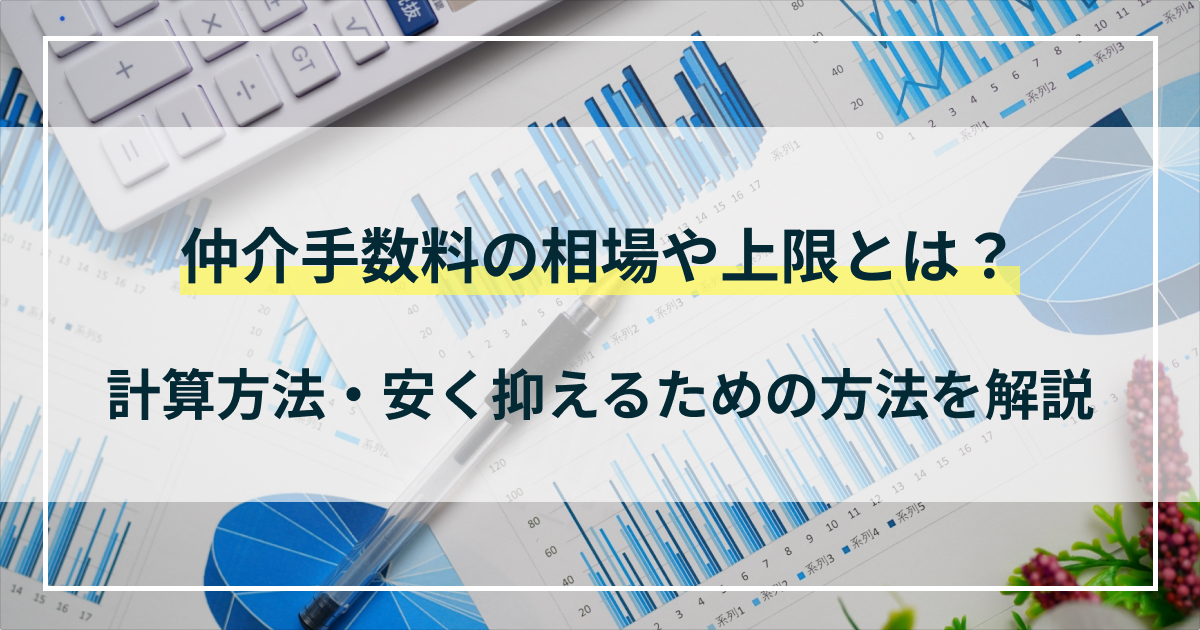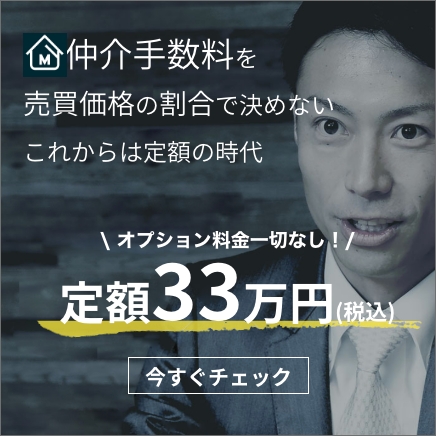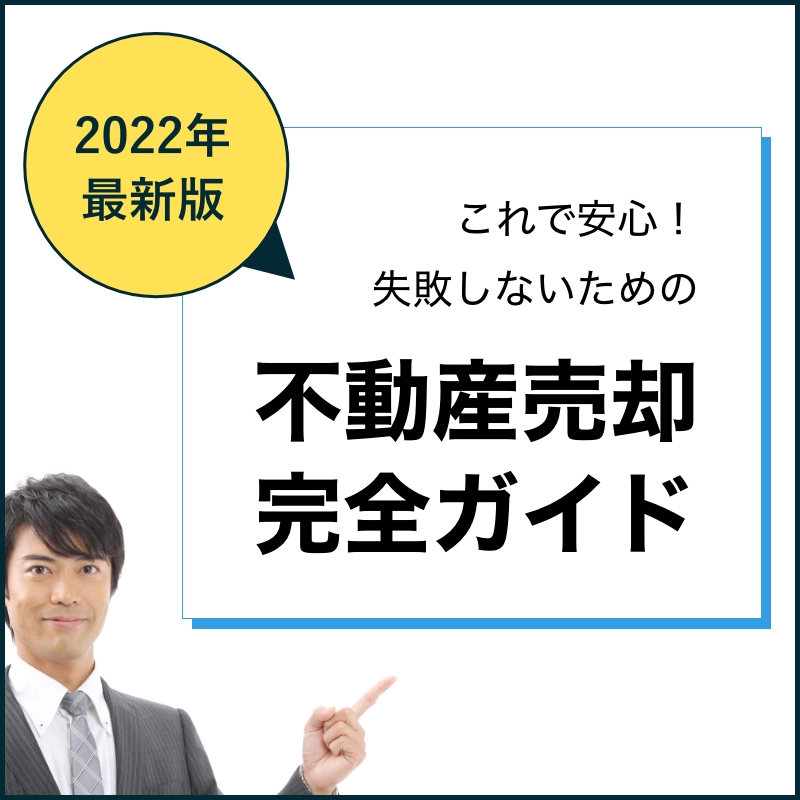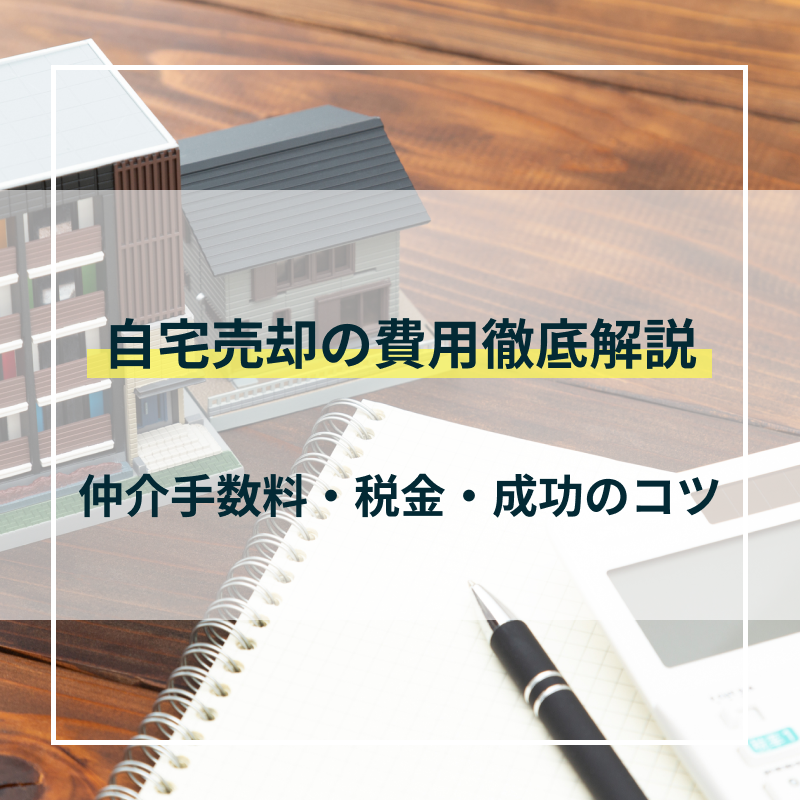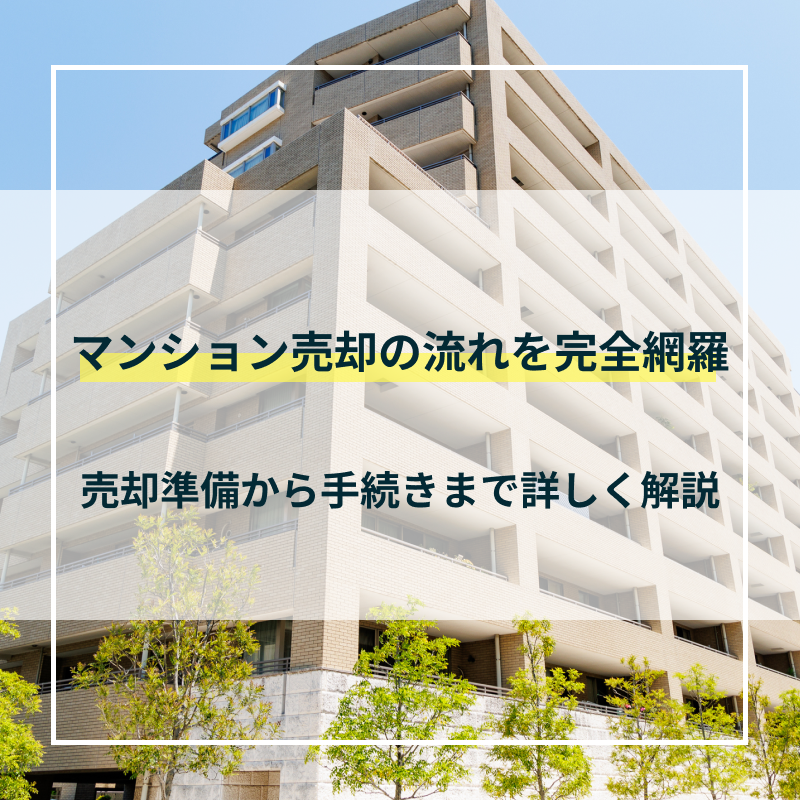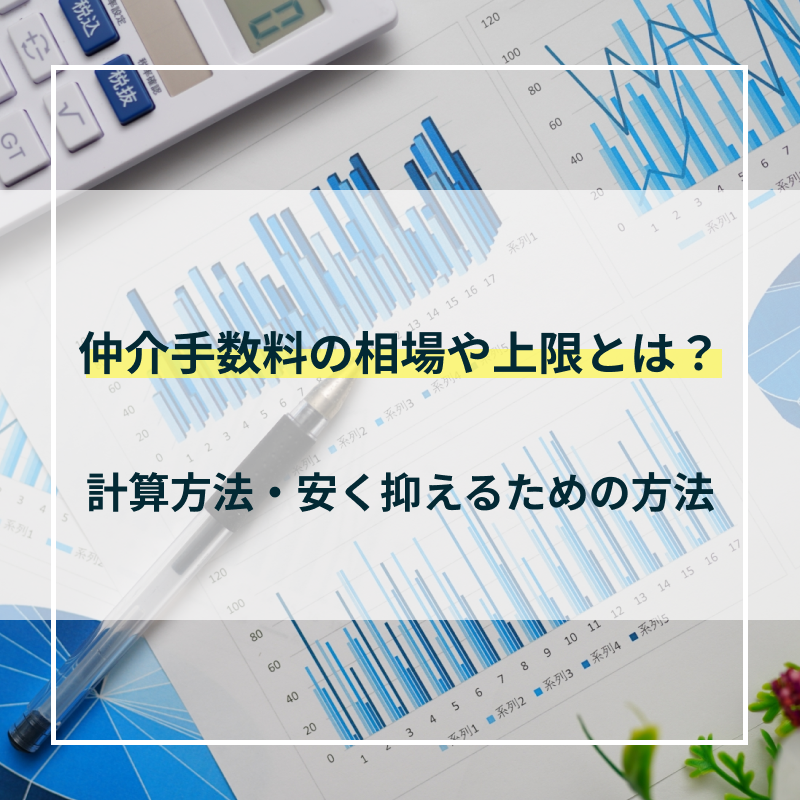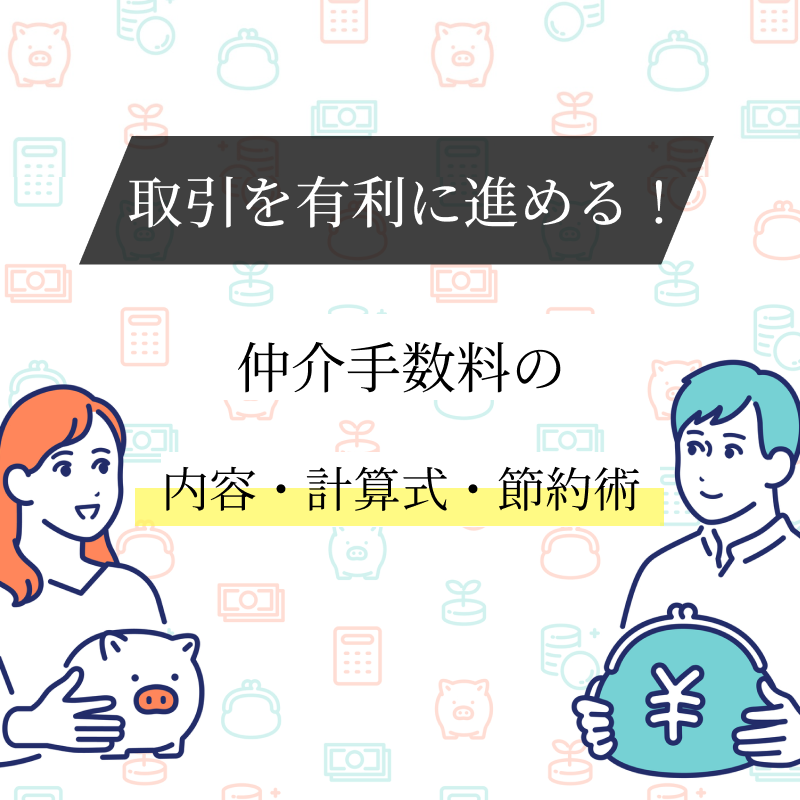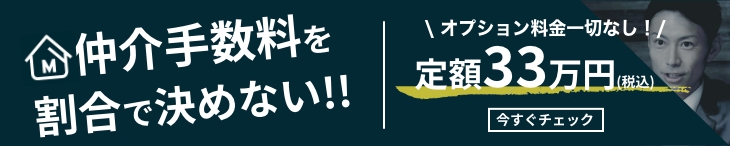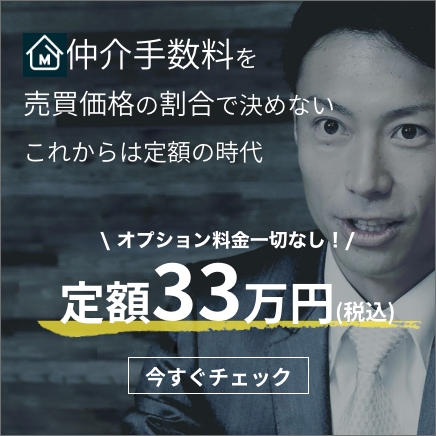
不動産を売買する際に、仲介会社を通して売買契約することで仲介手数料が発生します。今回の記事では、仲介手数料の計算方法や支払いが発生するタイミング、仕組みや業務内容など余すことなく徹底解説します!
- 仲介手数料の基礎知識
- 仲介手数料が発生するタイミング
- 仲介会社と結ぶ媒介契約の種類
不動産を売買する際、仲介会社を通して売買契約すると仲介手数料が発生します。
この記事では、仲介手数料の計算方法や支払いが発生するタイミング、安くする方法や注意点などを余すことなく徹底解説します。
不動産売却の仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産の売買が成立したあとに、仲介した不動産会社が受け取る成功報酬です。
仲介手数料について、おさえておくポイントは以下の4つです。
- 仲介手数料の上限
- 仲介手数料の早見表
- 仲介手数料の計算方法
- 仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料の上限
仲介手数料には「宅地建物取引業法」という法律で上限が定められていて、上限以上に請求することは禁止されています。
仲介手数料無料と宣伝している不動産会社以外は、上限まで仲介手数料を請求するのが一般的です。
下限が決まっていないので、不動産会社が応じれば仲介手数料の値引きや無料をしてもらえるケースもあります。
仲介手数料の早見表
不動産売買での仲介手数料の上限を一覧でご紹介します。売買価格によって大きく差がでることがわかります。
| 不動産の成約価格 | 仲介手数料(10%税込み) |
|---|---|
| 200万円 | 110,000円 |
| 400万円 | 198,000円 |
| 600万円 | 264,000円 |
| 800万円 | 330,000円 |
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 1,200万円 | 462,000円 |
| 1,500万円 | 561,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 2,500万円 | 891,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 3,500万円 | 1,221,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 |
| 4,500万円 | 1,551,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
| 6,000万円 | 2,046,000円 |
| 7,000万円 | 2,376,000円 |
| 8,000万円 | 2,706,000円 |
※「安い空き家の売買に関する特例」を参照してください。
仲介手数料の計算方法
手数料の計算方法は、以下の2種類があります。
- 速算式で計算する方法
- 売買価格を3つにわけて計算する方法
速算式で計算する方法
(売買価格×3%+6万円)×1.1
(売買価格×4%+2万円)×1.1
(売買価格×5%)×1.1
| 売買物件価格の例 | 計算方法 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 4,000万円の物件の場合 | (4,000万円×3%+6万円)×1.1 | 138.6万円 |
| 300万円の物件の場合 | (300万円×4%+2万円)×1.1 | 15.4万円 |
| 150万円の物件の場合 | (150万円×5%)×1.1 | 8.25万円 |
上記の表のように、売買価格によって計算式が違いますが、仲介手数料を計算したい物件価格の式に当てはめるだけなので、1度に簡単に算出可能です。
また、仲介手数料は課税対象になるので消費税分である「×1.1」も計算式に入れてあります。
速算式のなかにある「+6万円+2万円」とは、3つにわけて計算した仲介手数料の金額と合わなくなるので調整するためのものです。
「+6万円」と記載があると多めに取られていると勘違いしそうになりますが、合計金額を調整する、多めに請求しているわけではないので安心してください。
売買価格を3つにわけて計算する方法
売買価格を3つにわけて計算する方法は、以下の通りです。
- (200万以下の部分×5%) ×1.1消費税
- (200万超え400万円以下の部分×4%) ×1.1消費税
- (400万を超える部分×3%) ×1.1消費税
例:4,000万円の物件の場合
| 区分 | 3つにわけた金額 | 計算方法 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 200万以下の部分 | 200万円 | (200万円×5%)×1.1消費税 | 11万円 |
| 200万超え400万円以下の部分 | 200万円 | (200万円×4%)×1.1消費税 | 8.8万円 |
| 400万を超える部分 | 3,600万円 | (3,600万円×3%)×1.1消費税 | 118.8万円 |
| 合計金額 | 4,000万円 | 138.6万円 |
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料は成功報酬になるので、売買契約が成約後に請求できる報酬です。
そのため、数多くの物件の案内を受けていたり、紹介を受けていたりしたとしても売買契約が結ばれなければ仲介手数料は発生しません。
売買契約後であれば全額請求できますが、売買契約後に全額請求する会社は少なく、主に2通りの支払いタイミングがあります。
- 売買契約後に50%、引き渡しのときに50%の支払い
- 売買契約後に0%、引き渡しのときに100%の支払い
一般的には①のケースが多くなりますが、引き渡しまでの業務を完了してから一括で請求する会社もあります。
不動産の売買価格は関係なく、仲介する会社の経営方針によって異なります。
そのため、事前にどのタイミングで支払うのかを確認しておくことが大切です。
仲介手数料は、現金で支払うことが多く、支払いのタイミングまでに現金の用意が必要です。
振り込みに対応している会社もありますが、手数料が発生します。
不動産売却における仲介手数料の仕組みと業務内容
この章では、仲介会社が仲介手数料を貰う仕組みと仲介業務の内容を解説します。
仲介手数料には両手仲介と片手仲介がある
仲介会社が仲介手数料を貰う方法には「両手仲介」「片手仲介」があります
片手仲介
- 売主か買主どちらか一方の仲介のみをおこなう方法売主と買主がそれぞれ別の仲介会社と媒介契約を結んでいる状態
両手仲介
- 1つの物件に対して売主と買主どちらも仲介する方法仲介会社は仲介手数料をどちらからも貰えるため単純に片手仲介の2倍の報酬になる
仲介手数料に含まれる業務内容
仲介手数料に含まれる業務内容は不動産を売却するのか購入するのかで異なります。
| 売却する場合の業務内容 | 購入する場合の業務内容 |
|---|---|
| ・物件価格をいくらで売却するのか査定
・物件情報サイトへの掲載 ・チラシ作成 ・広告費や宣伝活動費 ・引き渡しまでの事務手続きや売買契約書などの作成業務 ・物件の内覧会での立ち合いや購入希望者への説明 |
・物件の紹介や案内業務
・主との値引きなどの交渉業務 ・引き渡しまでの事務手続きや売買契約書などの作成業務 ・住宅ローンの斡旋(別途費用として請求される場合もある) |
売却の場合、チラシ作成費用や広告費用も仲介手数料に含まれるので別途費用を請求されることはありません。
しかし、特別にお金をかけてチラシを作成するように依頼をした場合には、その分の費用を請求されます。
不動産売却において仲介会社との媒介契約
仲介会社と結ぶ契約には、以下の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約
一般媒介契約は、3つの媒介契約のなかで一番縛りが少ない契約です。
メリット
- 1度に複数の仲介会社と結ぶことができる契約方法になります。そのため、幅広く物件を紹介されたり案内されたりすることが可能になります。
- 自分で契約する相手を探すこともできます。もし、媒介契約を結んだあとに直接契約できる相手が見つかったとしても、問題なく売買契約を結ぶことができます。その場合には、仲介手数料の支払いは発生しません。
- 契約期間の定めがありません。契約期間を気にせず売買活動をすることができます。
デメリット
- 仲介会社からの報告義務がありません。そのため、売却の場合であれば購入希望者がどれだけ集客できているのか、物件の問い合わせ数はいくつなのか知ることができません。
- 仲介会社の優先順位が下がる可能性もあります。一般媒介は複数の会社に依頼できることから、いつの間にかライバル会社に先に売買契約を結ばれる可能性も十分にあります。そのため、がんばった分の仲介手数料を回収できないことも考えられるため、専任や専属専任媒介契約を優先される可能性があります。
専任媒介契約
専任媒介契約は、3つのなかで中間の条件になります。
メリット
- 自分で探してきた相手と直接契約できます。契約期間中だったとしてもこの場合には仲介手数料は発生しません。
- 物件情報サイト「レインズ」へ7営業日以内に登録することになります。レインズとは不動産業界では毎日チェックするサイトになります。そのため、早めに登録することで売却活動が有利になります。
- 2週間に1回以上の業務報告があります。必ず報告を定期的に受けることから安心して売買活動ができます。
デメリット
- 1社の仲介会社のみ結べる契約方法になります。そのため、依頼をした仲介会社の能力が低い場合、売買活動が難航する恐れがあります。
- 契約期間があり3か月以内とされていますが、多くの不動産会社が3か月間としています。この契約期間中に他の会社に依頼することはできません。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、一番縛りが強く仲介会社としては嬉しい契約方法です。
メリット
- 物件情報サイト「レインズ」へ5営業日以内に登録することになります。
- 1週間に1回以上の業務報告義務があります。1週間に1回以上なので、より早く正確な情報を知ることができます。そのため、今後の売買活動をどのようにするかの判断がしやすくなります。
- 不動産会社の優先順位が上がる可能性があります。他社や売主買主が自分で相手を見つけていつの間にか売買契約が結ばれる心配がない契約方法です。そのため、安心して仲介業務をおこなえます。仲介手数料を回収できる見込みが一番高いため、積極的に仲介業務をおこなってくれる可能性があります。
デメリット
- 1社の仲介会社のみ契約する方法です。専任媒介契約と同様に依頼した仲介会社の能力が売買活動の成功に大きく影響を与えます。
- 契約期間が3か月以内と定まっています。
- 自分で相手を見つけて直接契約することはできません。
不動産売却の仲介手数料を安くするポイント
不動産売却の仲介手数料を安くするポイントは、以下の3つです。
- タイミングを間違えない
- 不動産会社を見極める
- 仲介会社を通さず直接契約する
タイミングを間違えない
値下げ交渉するには、タイミングを間違えないことです。
仲介会社に相談する最初の段階で値下げの話をするのはよくありません。
営業マンのやる気がなくなり、相手にされない可能性がでてきます。
値下げ交渉のタイミングは、媒介契約を結ぶ前です。
値下げに応じれば媒介契約を結ぶことを条件に交渉します。
他社を引き合いにだして、迷っていることをアピールすることも重要なポイントです。
他社に取られないように値下げに応じる可能性が高くなります。
不動産会社としては他社にいつの間にか先を越される心配がない専任媒介契約を結びたいと考えます。
そのため、媒介契約を一般媒介ではなく専任媒介や専属専任媒介を結ぶことでより値下げ交渉が通りやすくなります。
媒介契約の種類については、「不動産売却において仲介会社との媒介契約」で解説しています。
不動産会社を見極める
値下げキャンペーンをしている会社
値下げキャンペーンやギフト券プレゼントなどのイベントを定期的におこなっている会社があります。
キャンペーンの時期であれば、値下げ交渉することも気まずくなく、仲介手数料を安くできる可能性があります。
値下げキャンペーンなどの狙いは、顧客を多く獲得することです。
値下げによって回収できる利益が減っても、契約数を増やすことで利益を回収する意図があります。
利用する側は支払う仲介手数料が少なくなってお得ですし、仲介会社側は顧客数を増やして利益を回収できるので、どちらにもメリットがあります。
大手より中小企業
大手企業より地域密着型の中小企業のほうが、値引き交渉が通りやすくなります。
なぜなら、値引きしてでも顧客を獲得したいと考えるからです。
大手企業であれば、値下げをしなくても顧客の集客に困ることはありません。
値下げするより利益を確実に回収することを選ぶ傾向にあります。
しかし、中小企業であれば大手企業に顧客を取られないためにも、サービス面で差別化をはかることが重要です。
そのため、値引きサービスや値引きキャンペーンをおこなう機会も多くなります。
また、大手企業より値下げを承諾できる権限を持っている上司までの距離が短くなります。
すぐに店長に交渉することも十分可能です。しかし、大手企業の場合、権限を持っている上司までの距離が遠く、数日かかることも考えられます。
両手仲介している会社
両手仲介の場合、売主と買主どちらからも仲介手数料が貰えるので、片手仲介に比べると単純計算で2倍の報酬になるため、片方からの仲介手数料を無料にすることも可能です。
仲介会社のなかには、「当社を通すと仲介手数料無料で物件を購入できます!」と宣伝している会社があります。
こちらは、最初から売主または買主の片方からのみ仲介手数料を貰うことを前提にしています。
売主と買主どちらからも仲介手数料を貰ったほうが利益は回収が簡単です。
しかし、仲介手数料は不動産価格によって異なりますが、100万円〜200万円ほどになり高額です。
そのため、仲介手数料を値引きしたい、無料にしたいと考える顧客は数多くいます。
昔と違いインターネットで検索すればすぐに無料で仲介してくれる不動産会社を見つけられます。
仲介手数料無料と宣伝している会社を利用すれば、値引き交渉する必要もなく物件の売買が可能です。
仲介会社を通さず直接契約する
仲介手数料は、仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。
そのため、仲介会社を通さずに自分で相手を探して直接契約をおこなえば仲介手数料を支払う必要はありません。
しかし、購入も売却も直接契約する場合は十分注意する必要があります。
売主から直接物件を購入するケース
売主とは、住宅であれば物件の施工主であり、土地であれば土地の所有者です。
売主が法人であれば不動産会社のプロとして、契約から引き渡しまでスムーズにおこなってくれます。
物件の施工主でもあるので、購入する物件のことに関しては、仲介会社より詳しいので質問に対しても素早い回答が期待できます。
また、売主から直接購入することで、売主も仲介業者に対して仲介手数料を支払う必要はありません。
そのため、物件価格に対しての値引き交渉も通りやすくなります。
ただし、仲介業者を通さないことで、他社が施工した不動産を紹介されない点には注意が必要です。
基本的に、売主は自分で施工した物件を紹介しますが、顧客の条件に合った物件のみを紹介するため、圧倒的に紹介できる数が少なくなります。
施工業者によって、住宅の造りや仕様、特徴などが異なります。間取りや価格が同じでも気にいる仕様も個人によってさまざまです。
多くの物件を見て検討したいと考える人には、売主と直接契約するより仲介会社を通して契約するほうが向いています。
また、売主だからといって必ず直接契約してくれるとは限りません。
仲介会社を通さないと売却しないということもあります。そのため、最初に直接契約できるか確認が必要です。
買主と直接契約して物件を売却するケース
買主を自分で見つけて直接契約することもできます。
その場合、仲介手数料は発生しません。
もともとの知り合いに売却するのであれば、チラシ作成や物件情報掲載などをして集客する必要もないため、短期間で売却することも可能です。
しかし、個人間での直接契約には大きなリスクが伴います。詳しくは「個人間売買はリスキー」を参照してください。
不動産売却の仲介手数料で注意すべきこと
不動産売却の仲介手数料には、以下の点に注意が必要です。
- 戸建て売買のときに売主が法人である場合の消費税
- 安い空き家の売買に関する特例
- 仲介手数料が発生するタイミング
- 売買契約後のキャンセル
- 個人間売買はリスキー
- 仲介手数料の安さを優先するのはNG
戸建て売買のときに売主が法人である場合の消費税
仲介手数料を計算するときに、戸建てを法人から購入する場合には、建物価格から消費税を引いて計算する必要があります。
あくまで「売主」が「法人」の場合で「住宅」を購入するときのみです。
個人間の取引や土地売買では関係ありません。
一般的に戸建ての売買価格には、土地と建物の価格の合計が記載されています。
土地は非課税になるのでそもそも税金は含まれていません。建物は、課税対象なので消費税が含まれています。
そのため、売買価格のうちの建物価格から消費税を引いて計算します。
建物と土地の内訳や比重は決まっていません。物件ごとに異なりますので、売主に確認する必要があります。
【例:4,000万円の戸建ての場合の内訳 土地:1,800万円 建物:2,200万円】
2,200万円÷1.1=2,000万円
1,800万円+2,000万円=3,800万円(税抜きの物件価格)
上記の計算のように、建物価格から消費税を引くことを最初にします。
税抜き価格にした金額を速算式などに当てはめて仲介手数料を算出します。
(3,800万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 132万円
4,000万円の売買価格でも、消費税を引くことで仲介手数料の上限が132万円になります。
建物価格の消費税を引くことを知らない不動産の営業マンもいるので注意が必要です。
安い空き家の売買に関する特例
2018年1月1日から、価格が400万円以下の安い空き家などの不動産売買において、仲介手数料に調査費用を追加できる特例が施行され、仲介手数料として最大18万円+消費税まで請求できるようになりました。
ただし、仲介手数料が一律18万円というわけではなく、売却に関する必要経費をプラスして請求できるようになったのです。
この制度は、空き家問題の解決を目指し、空き家の売買を促進するために導入されました。
空き家の売却は、通常よりも多くの費用がかかるため、不動産会社にとっては取り扱いが難しいものでした。
しかし、安い空き家でも仲介手数料18万円に必要経費をプラスして請求できるようになったのです。
追加費用については、不動産会社との契約時に説明を受け、合意が必要です。
参考:公益財団法人不動産流通推進センター|低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例
仲介手数料が発生するタイミング
仲介手数料は成功報酬になるので、売買契約が成約後に請求できる報酬になります。
そのため、数多くの物件の案内を受けていたり、紹介を受けていたりしたとしても売買契約が結ばれなければ仲介手数料は発生しません。
売買契約後であれば全額請求可能ですが、売買契約後に全額請求する会社は少なく、主に2通りの支払いタイミングがあります。
- 売買契約後に50%、引き渡しのときに50%の支払い
- 売買契約後に0%、引き渡しのときに100%の支払い
一般的には①のケースが多くなりますが、引き渡しまでの業務を完了してから一括で請求する会社もあります。
不動産の売買価格は関係なく、仲介する会社の経営方針によって異なるため、事前にどのタイミングで支払うのかを確認しておくことが大切です。
仲介手数料は、現金で支払うことが多く、支払いのタイミングまでに現金を用意しておく必要があります。
振り込みに対応している会社もありますが、手数料が取られます。
売買契約後のキャンセル
売買契約後に売買をキャンセルした場合、キャンセル理由によって仲介手数料の支払いが発生することがあります。
仲介手数料が発生しないケース
- 住宅ローンが通らなかった
- 住むことが困難なほどの隠れた瑕疵が見つかった
- 自然災害により住宅が倒壊等した
- 契約書に記載してある特約条件を満たせなかった
上記のように自分の責任ではないことが理由でキャンセルする場合には、売主と買主が合意の上、「白紙解約」することになります。白紙解約とはもともと契約がなかったことになる解約方法です。もともと契約がなかったことになるので仲介手数料の発生はしません。
一番数として多いのが住宅ローンの審査が通らないことでの白紙解約になります。住宅ローンには事前審査と本審査があり、売買契約前に事前審査を受けて通っても、本審査で通らないケースもあります。
仲介手数料が発生するケース
- 転勤することになったので購入しても住めないため解約
- 親からの反対による解約
- 契約書に記載している違約事項をおこなった
上記のようなケースは、自己責任ではないように思えますが、売買契約上では自己都合扱いになり、仲介手数料の支払いが発生します。また、売主に対しても手付金を放棄したり、違約金を支払ったりすることになります。
この場合、引き渡しまで完了していませんが全額仲介手数料を支払うのか半分支払うのかは仲介会社との媒介契約書の内容によって異なります。
個人間売買はリスキー
買主が個人の場合には注意が必要です。
専門的な知識もない個人が売買契約書を作成し、不動産という高額な取引をおこなうには大きなリスクがあります。
住宅の瑕疵を知っていたのに記載するのを忘れてしまった、設備機器に関して故障していたことを記載し忘れたなど、騙すつもりはなく記載することを忘れていただけでも、後々大きなトラブルに発展します。
違約金や損害賠償を請求されることもあるかもしれません。
個人に売却する場合、多くの場合売却する相手は知り合いや隣人です。
しかし、信頼している相手でも金額が大きい売買になるので、引き渡し後にトラブルになることは十分考えられます。
そのため、個人への売却の場合には不動産会社を通してプロに売買契約書や重要事項説明書などの作成依頼をおすすめします。
不動産売却における仲介手数料で安さを優先するのはNG
不動産売却における仲介手数料で、安さを優先するのはおすすめしません。
仲介手数料が半額や無料で、売買価格を低くされて売却されるより、上限の仲介手数料でも、高く売却できたほうが、結果的に利益が増える可能性があります。
「安さ」にこだわるより、「信頼できる会社」を優先することで、満足度の高い売却の可能性が高まります。
オススメ記事
簡単に自動計算!【土地編】売却の仲介手数料はいくら?相場や無料の仕組み、値引きポイントを解説
この記事では、土地の売却方法に焦点をあてながら、不動産売却時にかかる仲介手数料について解説していきます。合わせて自動計算ツールもご紹介しますので、大まかな仲介手数料を把握したい人はぜひこちらもご利用ください。

まとめ
仲介手数料は不動産価格にもよりますが高額になりがちです。
そのため、簡単に支払えるものではなく仲介手数料を少しでも安くしたい、無料にしたいと考える人は大勢います。
しかし、仲介手数料がどういった仕組みなのかなどの基礎知識がないと、対応が難しくなります。
今回解説した仲介手数料の内容を参考にしていただき、不動産売却を優位におこなって頂ければと思います。
その他不動産に関するお悩みをお持ちの方は、マスターズコンサルティングにお気軽にお問合せください。