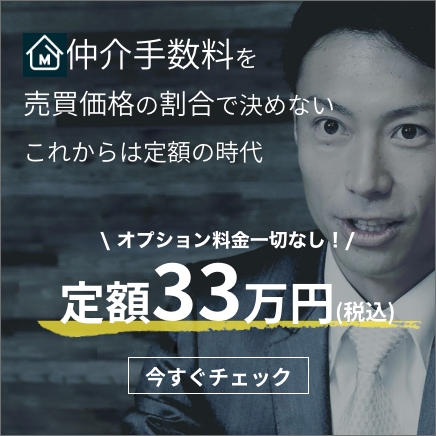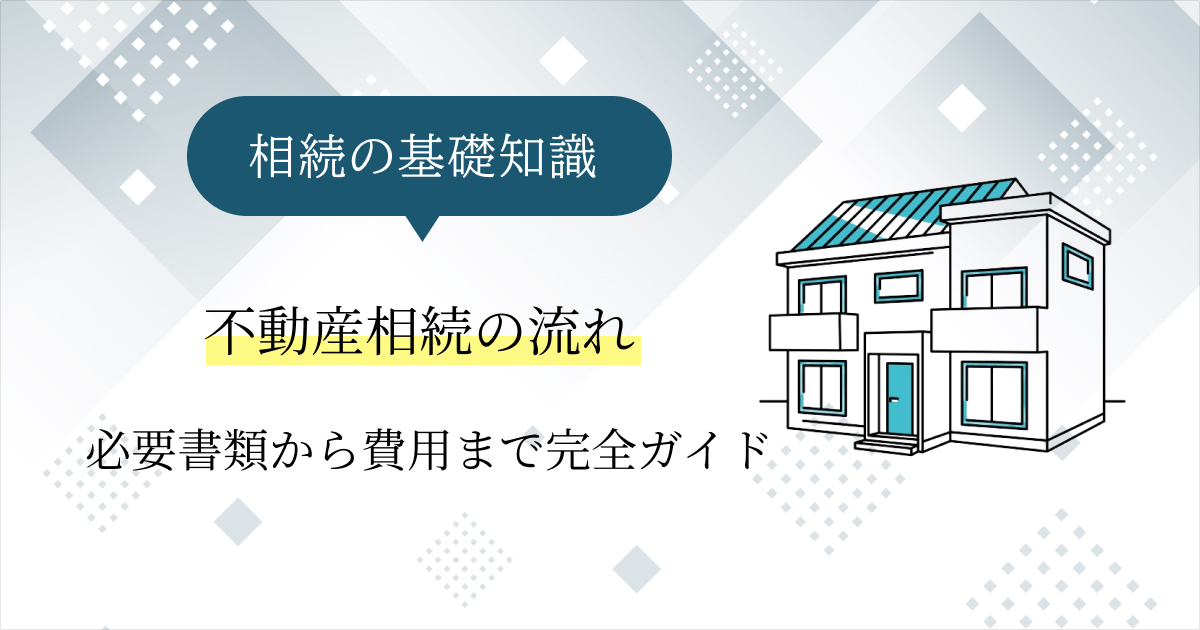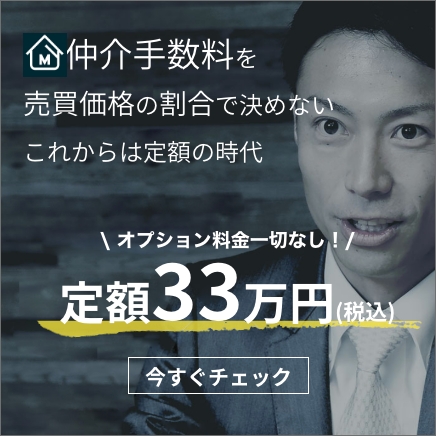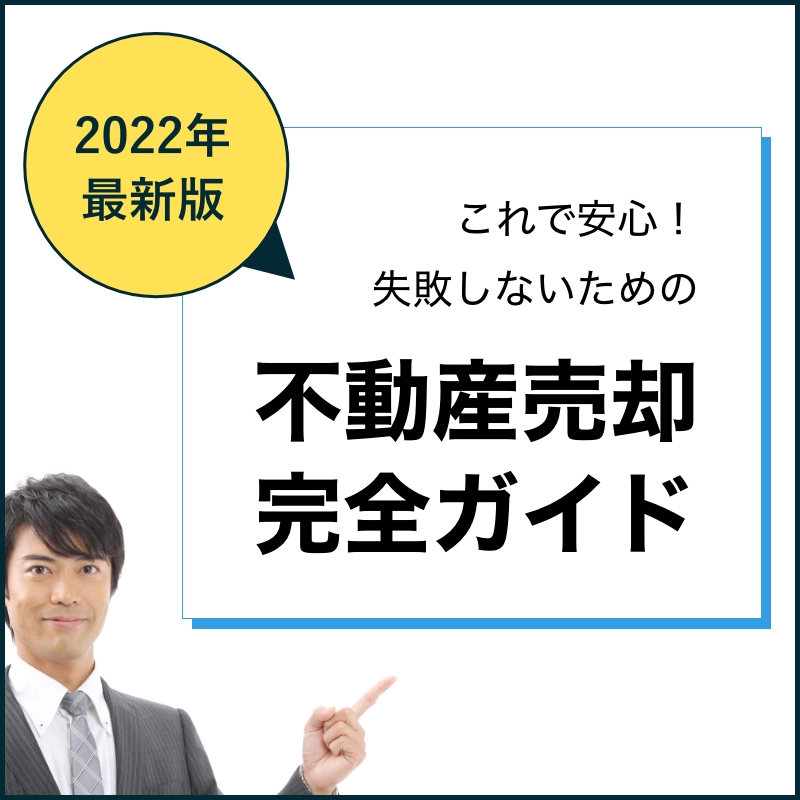相続財産のなかに不動産が含まれているときは、相談するにあたってとかく相続人同士でトラブルが生起しやすくなります。
それは不動産が単体として分離することができない財産であることが主たる原因であります。
しかも不動産の大小にかかわらず生起しますので、一部の富裕な資産家などに限定された特別なことではなく、ごく普通の家族にこそ起こりやすいトラブルなのであります。
また、長年親の面倒をみている、親と長く同居している、あるいは疎遠になって兄弟姉妹がいるなど家族の事情はさまざまであり、いざ相続というときに際して、それぞれの主張も出てきて収拾がつかなくなる可能性があります。
このように不動産相続をめぐる争い、決して他人事ではないのです。
不動産相談をめぐって家族が互いに骨肉の争いをすることのないように、不動産相続トラブルの事例とその対策を事前によく研究し、準備をしておくことが肝要であります。
そこで今回は、不動産相続によるトラブルはどのようなケースにおいて発生するのか、その代表的な事例とその解決策について具体的にご紹介していきたいと思います。
事例1:相続人同士でトラブルになるケース
相続時には、相続人の数が多いほどトラブルになる可能性が高くなります。
とりわけ不動産が相続の対象となる場合は分割方法をめぐって遺産分割協議がまとまらずトラブルに発展する可能性が高くなります。
また親に離婚歴があって、認知していた子どもや前妻の子どもが名乗り出ることによって一人当たりの相続分が減るため、遺産分割協議が白紙に戻ってしまうこともあります。
親に離婚歴がある場合や愛人が存在していると認められるようなケースは、あらかじめ本人に事実確認をしておくことが重要です。
また相続人が複数人いる場合は、法定相続分だけで解決しきれないことがあります。
これらの予防策としては、遺言書を作成しておくことが非常に有効になりますので、場合によっては切り出しにくいかもしれませんが、相続人同士での骨肉の争いを回避するためにも、親(被相続人)が元気なうちに遺言書を作成しておくように進言するのが懸命です。
オススメ記事
【2023年相続税法改正】生前贈与加算の期間延長を徹底解説!
この記事では、2023年税制改正による生前贈与加算の期間延長について解説していきます。課税の対処法もご紹介しておりますので、計画的に子供や孫へ資産を移し、相続税の支払いを抑えるのに役立てば幸いです。

事例2:相続した不動産を平等に分割しようとするケース
普段は相続人である兄弟姉妹の仲がどんなによくても、トラブルになってしまうことがあります。
それは相続人に互いに損得ないように平等に分割しようとして、却って揉め事に発展しまうケースです。
不動産は姿形そのままで平等に分割するのがむずかしい資産であるのみならず、不動産価額の指標が複数存在していますので、どの指標を採用するのかについて意見が分かれて対立してしまうことがあるからです。
不動産を平等に分割する方法には大別して「換価分割」「現物分割「共有分割」」という3つの方法があります。
このなかで「換価分割」が最もトラブルを回避することができる方法であると言えます。
換価分割
換価分割とは相続不動産を売却して得た現金を相続人で分けるという方法です。
たとえば相続人が3人兄弟で、不動産の売却価格が2,000万円の場合、売却にかかった費用が200万円だったとすれば、手元に残っている1,800万円を分割して、1人600万円ずつ受け取ることができることになります。
現物分割
現物分割は相続する不動産をそのままの姿形で分割する方法です。
3人兄弟が相続する場合、不動産を3人で分筆(土地)分割(建物)して、それぞれ所有することになるのです。
売却などの手間がかからず、不動産をそのままの姿形で受け継ぐことができますが、分筆された土地の方位や形状、接道位置はそれぞれ異なりますので、面積が同じであっても換価には差が出てしまうために、真の意味で公平に分けることができる物件はごく僅かになります、さらに土地の上に建物がある場合には実際には土地の分筆は困難で不可能なことです。
更地であったとしても一般的な宅地規模であれば分筆によって現実には使いにくい狭小地になって、土地の有効活用は難しくなるうえに、それぞれの土地の評価額は大幅に下落してしまうリスクもあります。
共有分割
共有分割はひとつの土地を複数の相続人の共有名義にして相続する方法です。
3人兄弟が共有する場合は、それぞれの持分が3分の1ずつになります。
平等に相続することができる反面、共有名義は土地を活用するにあたってさまざまなデメリットがあります。
売却や建築には共有者全員の同意が必要になりますので、一人でも反対するとなにもできません。さらに相続人の子どもの世代や孫の世代に相続すると、持分のある共有者の数が増えることになって、ますます有効活用が難しい不動産になってしまいます。
また、固定資産税の納付についてもトラブルが発生することがあります。
共有名義での不動産の固定資産税は、共有持分に応じて課税されるものではなく、共有者全員が負担する「連帯納付義務」があります。
納税通知書は共有名義一つについて一通のみが代表者に送付されることになります。
したがって代表者は他の共有者から納税負担分を自ら徴収しなければならなくなって、納期ごとに煩わしい思いすることになり、しかも共有者の誰かが固定資産税を滞納した場合には、立替払いをしなければならない羽目になります。
共有分割は、表面的には不動産相続の簡便な解決方法であるように見えますが、このようなデメリットを考慮した場合は、決して良い選択であるとは言えないのです。
遺産分割協議がもつれてなかなか決着ができず、収拾がつかなくなった場合に用いられる最後の砦のような手法なのです。
事例3:不動産を相続すると不均衡が起こるケース
親と同居している子がいる場合、被相続人である親が死亡した後も引き続きその家に親と同居していた子が居住するのが一般的です。
住まいを確保するために、同居していた子は実家の土地や建物を相続したいと希望することでしょう。
しかしながら相続人が複数存在している場合は、相続分をめぐってトラブルに発展する可能性が出てきます。
その相続不動産に一定の価値があり、しかも実家以外にめぼしい相続財産が存在していない場合はなおさらです。
これらの解決策としては、相続人が複数存在したとしても不動産を一人の所有にせざるを得ない場合には不動産を相続した相続人が他の相続人に現金を支払うという代償分割が適しています。
たとえば3,000万円の不動産を3人兄弟の長男が相続する場合においては、長男が2人の弟に対して自分の資産のなかから1,000万円ずつ現金で支払うという方法です。
したがって不動産を相続する相続人は他の相続人に代償金として支払うだけの資産を有していることが前提条件になります。
もっとも代償金として支払うことができるだけの資産を有していたとしても、相続の対象となる不動産の評価額をめぐってトラブルになることも少なからずあります。
ここで採用することができる価額は、「相続税評価額」か「代償分割時の時価」のいずれかになります。
相続税の算定基準にする場合は、相続税評価額が基本になりますが、相続税評価は実勢価格の80%程度であるため、この価額を採用すると代償金を受け取る相続人が納得しない可能性が高くなります。
したがって実際には、「代償分割時の時価」を採用するケースが多くなっているのです。
同居していた子にとっては、親の所有していた家にそのまま住み続けることができるかどうかは重要な問題でありますので、将来的に実家を相続したいけれども代償金を調達することができないと想定される場合においては、できるだけ早い段階から他の相続人とじっくりと話し合って、理解を得るよう努力することが不可欠のことになります。
また被相続人である親が元気であるうちに、相続人同士の骨肉の争いに発展することを回避するためにも遺言書を作成しておいてもらえるように進言するということも有効な方法になります。
代償分割の注意点
代償分割を行う場合においては遺産分割協議書を作成して、金銭の譲渡が代償分割によるものである旨を明記しておく必要があります。
だれが何の遺産取得の代償としていくら支払うのかを明記しておかなければ、他の相続人が支払った金銭が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があるからです。
また、代償財産として現金の代わりに相続人が以前から所有していた不動産を譲渡すると、譲渡する側に譲渡所得税が課税される点にも注意する必要があります。
一見して不動産の交換であり利益は出ないようにも思われますが、税制上は代償金という負債を返済するために不動産を売却したものと解釈されるからです。
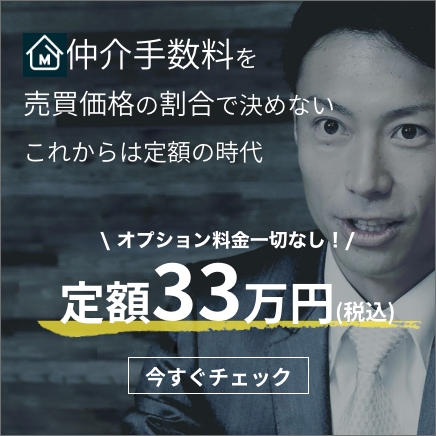
事例4:誰が不動産を相続するかで揉めるケース
親が住んでいた実家の不動産が、相続財産のなかで最も価値が高いというケースにおいては珍しいことではありませんが、資産に占める割合が高いときには、不動産の相続をめぐってトラブルになることがままあります。
とりわけ相続人の中に親と同居していた子がいる場合には、不動産を相続したいと強く主張することが多くなっています。
たとえば相続人が子ども3人である場合、親が遺した財産を3分の1ずつ相続するのですが、長年親と同居し世話や介護をしてきた子にとっては、なにもしてこなかった兄弟と同じ割合であるのは納得できないと思うのも無理もないことであり、遺産分割協議に応じて貢献度を考慮して欲しいと希望することでしょう。
民法ではこのような貢献度を遺産分割に反映される「寄与分」という制度があります。
相続人のなかに「被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした」者がいる場合寄与分の主張をすることができ、これが認められると他の相続人よりも多く財産を相続することができるのです。
さらに民法改正によって、たとえば嫁いできた長男の妻が長年被相続人の介護をしてきた場合のように相続人でなくても被相続人に対して特別の寄与をした親族であれば特別寄与料の請求すなわち不動産を相続することを主張することができるようになりました。
遺産相続において、旧民法ではまったく評価されなかった世話や介護の実績が、民法改正によって根拠を得ることになりました。
そのために貢献度の認識が大きく食い違うと、相続トラブルに発展することもあります。
改正前でも「寄与分」の制度がありましたが、相続人に限定されていました。
したがって、被相続人の長男の妻が介護に貢献していた場合、長男の寄与分として考慮して解決できることもありましたが、すでに長男が死亡し、遺言がない場合その妻はまったく遺産をもらえないことから不公平であるという指摘がありました。
そこで民法改正によって、2019年7月1日以後に開始した相続については、「特別寄与分」の制度が設けられ、相続人以外の親族で被相続人に対して特別の寄与をした者(特別寄与者)はその貢献が考慮され相続人に対して特別寄与料を請求することができるようになりました。のいずれかになります。
特別寄与者の要件
被相続人の親族(相続人および相続放棄者等を除く)親族とは被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族のことです。
親族以外の者、内縁の妻などは特別の寄与をしていたとしても特別寄与料の対象になりません。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をしたこと。
特別寄与料の計算方法
介護を行った場合の寄与料の算定方法は、介護報酬基準額を参考にして、日当額を決めて下記の算式によって算出します。
第三者の日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)
特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定し、相続人が、相続分で負担します。
なお、協議がまとまらない場合は家庭裁判所で決定することとなります。
また、家庭裁判所への申立てを行う期限は、特別寄与者が相続開始を知った時から6カ月以内または相続開始の時から1年を経過した日までになりますので注意が必要です。
寄与料の支払金額は、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。遺言がある場合は注意しなければなりません。
必要な書類(証明書)特別な寄与をしていたと証明できるものが必要になります。
たとえば、介護をしていた場合には介護日誌やその介護に伴って支出した費用の領収書などがあります。
その他、被相続人との連絡の記録やメール、手紙などは残しておくことが望ましいと言えます。
※介護の内容によって金額および裁量割合は上下しますが、日当額6,000円、裁量割合0.7と仮定します 特別寄与料の額 6,000円 × 365日 × 0.7(裁量割合)≒ 約150万円
相続人は特別寄与者に対してそれぞれ相続分150万円×3分の1=50万円を支払う。
特別寄与料の支払いが確定した場合には、特別寄与料を取得した子の配偶者は150万円を被相続人より遺贈によって取得したものとみなして相続税の計算を行います。
申告期限は、その支払いが確定した日の翌日から10ヶ月以内になります。
その他、3年以内に被相続人からの贈与がある場合には、相続税の課税価格に参入されて、被相続人の子の配偶者であるため、その相続税額については2割加算の特例の適用があります。
また相続人である子の相続税の申告については、子は特別寄与料の支払いを行うために、そえぞれの特別寄与料額50万円は相続税の課税価格から控除します。
すでに相続税の申告を行なっている場合には、特別寄与料の支払いが確定した日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことができます。
特別寄与料は特別寄与者と相続人との協議によって決定されますので、協議がまとまらないケースも考えられます。
もし、生前に介護等の特別の寄与が発生している場合は、特別寄与料相当額を以下のような方法で事前に準備しておくのがよいのです。
- 遺言により特別寄与者へ遺贈を記載する(相続税課税、2割加算あり)
- 生前贈与により特別寄与者へ渡す(贈与税課税、暦年贈与110万円の非課税を利用)
- 特別寄与者を生命保険の受取人とする(相続税の非課税なし、2割加算あり)
- 介護について働きに応じてその都度支払を行う(所得税課税)
- 生前に父と養子縁組を行う(相続税課税、相続人)
被相続人である親としても、介護をしてくれた人やその家族に対しては深く感謝しているはずですが、気持ちだけでは相続に反映させることはできませんので、とりわけ資産のほとんどが自宅の不動産という場合においては、同居している相続人は親としっかりと話し合い、遺言書を作成してもらえるように進言しましょう。かつて自筆証書遺言書はすべてを自筆で書かなければなりませんでしたが、民法改正によって、自筆証書遺言書に添付する財産目録はパソコンによる作成が認められていますので、遺言書を作成する手間が大幅に削減できるようになっています。
また保管場所については、自筆証書遺言書を法務局または地方法務局で保管する制度が運用されています。
法務局または地方法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうと、紛失やどこに保管したかを忘れてしまう心配、あるいは廃棄されたり改ざんされたりする心配がなく、安心して遺言書を作成し遺しておくことができます。
オススメ記事
不動産を相続した場合において、その手続きの流れと必要書類、不動産の相続時に発生する税金、相続した不動産に関するトラブルを回避するための遺産分割方法などの注意すべきことをご紹介。

事例5:相続した不動産の名義変更ができていなかったケース
親が死亡して相続が開始したので、不動産の登記を確認してみると、物件の所有者が大昔に死亡していた祖父のままになっていたというケースが少なからずあります。
この場合は、祖父の相続から整理していくことになりますが、膨大な時間と労力を要します。
とりわけ親の兄弟姉妹が多人数の場合、相続人の整理や事務処理は、とうてい個人の力で行うことできるものではありませんので、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することになります。
解決策としては、不動産の名義人に一抹の不安がある場合には、親の元気なうちに登記の確認をしておくことが肝要であります。
有料のサービスになりますが、自宅からインターネットによって確認をすることができます。祖父の時代の相続は、当事者である親の主導でより早く解決することができます。
事例6:遺言書が問題でトラブルに発展するケース
相続のトラブルを回避するために最も有効な方法は遺言書の作成です。故人の遺志を明確にすることによって、相続人の不満を解消することができるからです。
ところが遺言書自体が原因となってトラブルに発展することがありますので注意する必要があります。
とりわけ次のようなケースの場合においては、遺言書の有効性をめぐって争いになる可能性があります。
- 遺言書の形式が無効である
- 遺留分を無視した遺言書の内容である
- 特定の相続人のみに相続させる内容である
- 第三者に遺産の全てを遺贈する内容である
このような相続財産の分割が著しく不均等な内容の遺言書であると、相続分が大幅に抑えられた法定相続人から異議が出され、遺言書の些細な瑕疵でさえトラブルに発展する可能性があります。
その解決策としては、まず遺言書の違法性を確認すること、すなわち故人の遺志を尊重して相続財産の分割を行うのが遺言書の役割でありますが、それを十全に実現するには、法的に適正な遺言書であることが必須の前提条件になります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方式がありますが、秘密証書遺言は一般にはあまり採用されることはありません。
また公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方法で作成されますので、遺言書の方式に関してトラブルになることはほとんどありません。
したが って法的に適正な遺言書であるかどうかが問われるのは、ほとんどのケースで自筆証書遺言書についてのことです。
一般に自筆証書遺言書が次のような状態である場合には無効であるとされてしまいます。
- 遺言書の本体をパソコンによって作成している、ただし相続財産目録はパソコンによって作成しても構わないことになっています
- 遺言書に押印がされていない
- 遺言書を作成した日付が記載されていない
- 明らかに遺言者以外の人間が作成した遺言書である
- 相続する財産が不明確
- 遺言書を作成した日付が明らかに虚偽である
- 動画や録音による遺言書である
これらの状態となっている遺言書は、訴訟になった場合においては無効であるとされる可能性が高く、その場合には改めて相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。
また自宅などに自筆証書遺言書が保管されている場合には、勝手に開封することは認められず、未開封のまま家庭裁判所に提出して、検認の請求を行い、相続人の立ち合いの下で開封することになります。
もっとも勝手に開封したからと言って、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、勝手に開封した者は5万円以下の過料の対象となりますので注意する必要があります。
このようなことから、相続財産をスムーズに分割するためには、遺言書の適法性を相続人の全員で確認することが重要なことになります。
次に解決策となるのは、遺留分侵害額減殺請求をすること、すなわち遺言書による明らかに偏った内容である場合においては、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の相続分のことです。
相続においては遺言書による財産の分割が優先され、しかも遺言者の自由意思によって、誰にどれだけの財産を相続させるかを決めることができますので、個人的に世話になった人など、法定相続人以外の者に相続財産を渡すこともできるのです。
しかしながらそのために法定相続人の遺産がゼロになるというのではあまりにも酷であるために、民法では被相続人の子や配偶者は、法定相続分の2分の1が遺留分として保障されているのです。
相続開始後に遺留分の侵害が判明すれば当該相続人が侵害している受遺者・受贈者に対して対して遺留分減殺請求をします。
これで相手方が遺留分を返還してくれるなら問題は解決するのですが、相手方が納得しなかった場合には、家庭裁判所において調停することになります。
調停手続きでは当事者双方から事情を聴取して、遺産を精査したうえで、当事者双方の意向に沿った解決策を提示してくれます。
調停でも解決することができなかった場合には、地方裁判所(訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所)に民事訴訟を提起して判決に従うという流れになります。
事例7:相続した不動産を「空き家」にするケース
親から実家を相続した場合、思い入れがあるために売却に踏み切れないで、空き家として維持することがあります。
しかしながら、空き家の状態で放置していると、思わぬリスクがあることを失念しがちです。
固定資産税が増加するリスク
空き家の状態で放置しておくと、想定していた以上の固定資産税課税と建物の劣化が進みます。
台風や豪雨の際にも対策を立てられないために、無防備で風雨にさらされて、いつしか崩壊寸前の状態になることもあります。
崩壊寸前の状態にある家屋は、地方自治体が特定空き家に指定することがあります。
特定空き家に指定された土地は、固定資産税の優遇税制が適用されなくなりますので、固定資産税が一気に数倍にもなることがあります。
犯罪リスク
空き家であることが周囲に知られると、不審者が侵入して勝手に住みつくことがあります。
犯罪者が潜伏したり、犯罪行為を行う拠点として利用されたりする可能性があります。
周辺住民のリスク
空き家であると庭木の手入れもなおざりになるために、雑草が生い茂ります。
このような雑草地は野生動物の巣窟になることもあります。また不法投棄の場所として利用されることもあります。
これらによって発生した悪臭などの不衛生な状態が、近隣の住宅に迷惑をかけることもありますので注意しなければなりません。
定期的メンテナンスや維持費の発生
空き家の劣化によるリスクを回避するためには、定期的なメンテナンスによる維持を欠かすことができません。
とりわけ空き家においては、定期的な家屋の換気が求められるために、自らが実家に赴くか代理人による作業を依頼することになります。
これらに要する交通費や依頼費の発生も念頭に置いておく必要があります。
外壁の劣化が早まる可能性があります。
室内に雨水が侵入すると加速度的に家屋が劣化するために、著しく経年劣化した建物であると本格的な改修工事が必要になります。
解決策としては、兄弟姉妹の構成上実家を相続する可能性が高い場合には、あらかじめ次のような対応策を考えておくべきです。
- 売却する
- 貸し出す
- 管理会社に管理を依頼する
- 家族で定期的に管理する
- 家族で住む
売却しようと思っても、人口の少ない地方ではなかなか買い手が見つからないことがあります。
仲介による売却が困難であると予測できる場合には、買い取り専門の不動産会社に買い取ってもらうという方法を検討するのがよいと思われます。
また他人に貸し出すという方法は、家賃収入のほかに建物を使用することによるメンテナンス効果が期待できます。
地方では、自治体やNPOなどによる空き家バンク制度を活用」する方法が有効です。
家族自らが管理するのは、自宅と距離が離れている場合には、金銭的にも精神的にも負担が大きくなりますので、注意しなければなりません。
新たな仕事が得られるめどが立つのであれば、自宅を売却して実家に移り住むという方法も考えられます。
まとめ
遺産分割事件になった約7割が遺産総額5,000万円以下の案件です。すなわち一般的な家庭にこそ、相続に関するトラブルの種が潜んでいるのです。
トラブルを回避するためには平等に分割するのが理想ではありますが、不動産が相続財産に含まれていると、なかなか思い通りには事は運びません。
相続人全員が納得する分割方法を遂行することが困難であるからです。
不動産を平等に分割する方法としては、換価分割、現物分割、共有分割、代償分割がありますが、最も平等に分割することができる方法は換価分割です。
相続不動産を売却した後に現金を分配するので、相続人の誰もが納得のいく方法でしょう。しかし実際には相続する際に同居家族が存在する場合には、容易に売却することができません。
その場合には、他の相続人に自宅の不動産の価額に相当する代償金を渡す代償分割が適しています。
ただし実際に渡せるだけの現金を調達できなければこの方法は実行できません。
あらゆる相続について言えることでありますが、トラブルを回避することができる最善の方法は遺言書による相続です。
法的に有効な遺言書であれば、遺留分を侵害しない限り遺言通りに相続財産を分割することができます。
とくに相続財産のなかに不動産が含まれているようなケースにおいては、現実には平等に分割することは困難であるために、遺言書が存在することは非常に重宝なものになります。
親が持ち家に住んでいるのであれば、親が元気なうちに相続をテーマにした話し合いの機会を設けて、遺言書を作成しておいてもらえるように進言することが有効な方法です。
それが将来の相続をめぐるトラブルを回避する道に通じるのです。