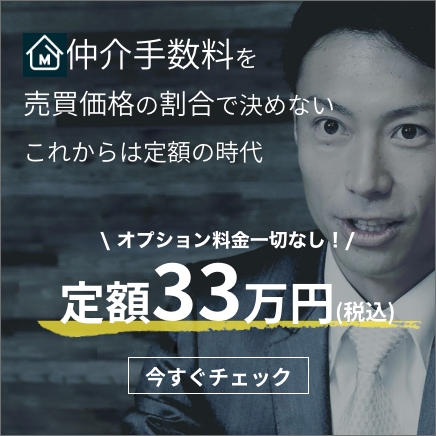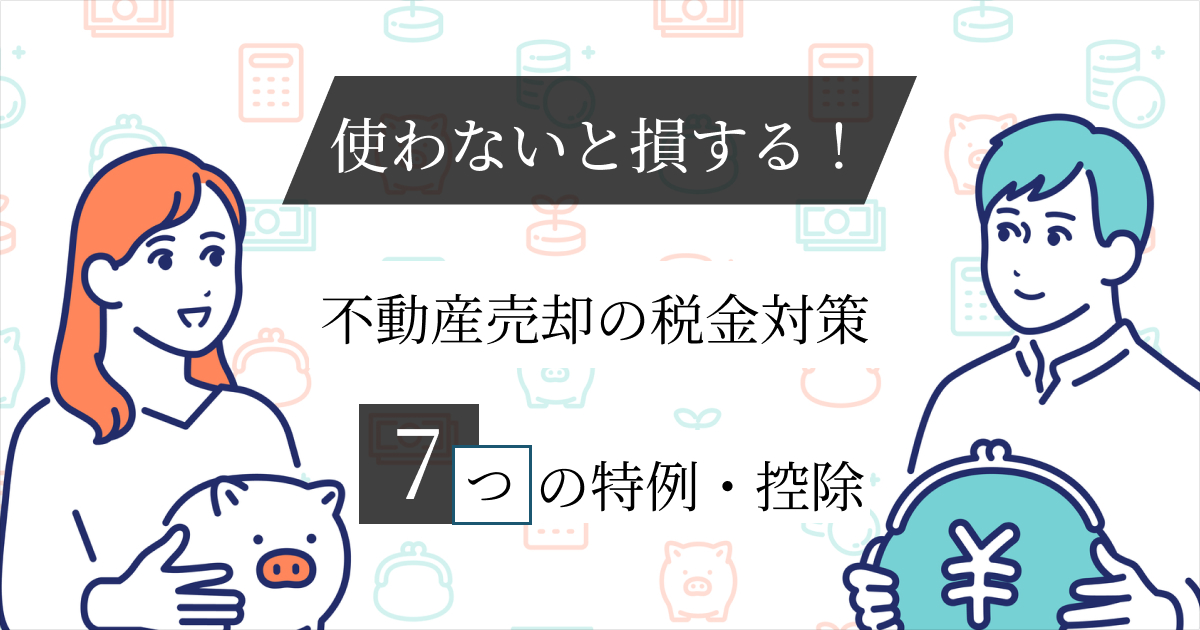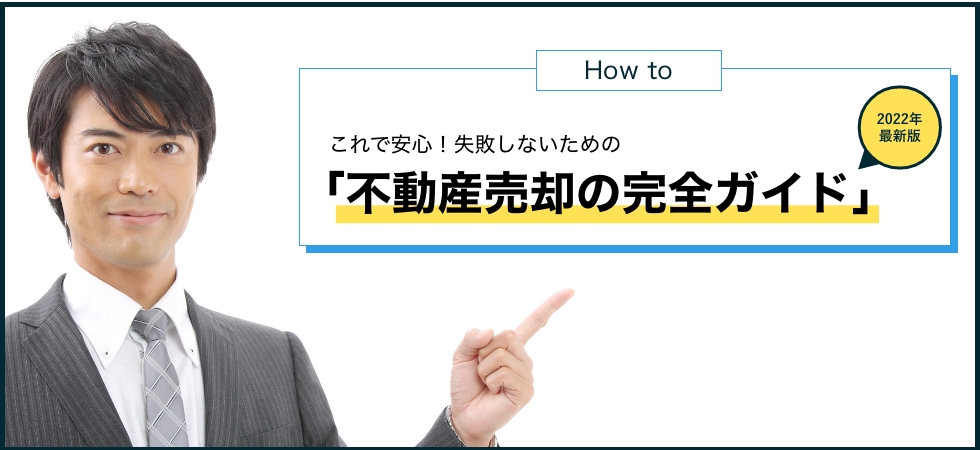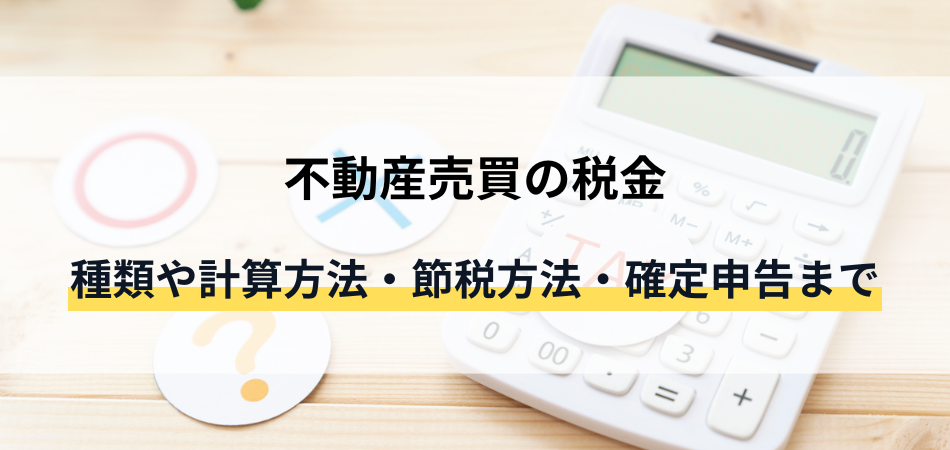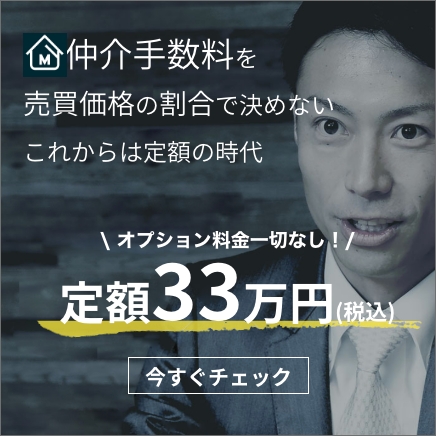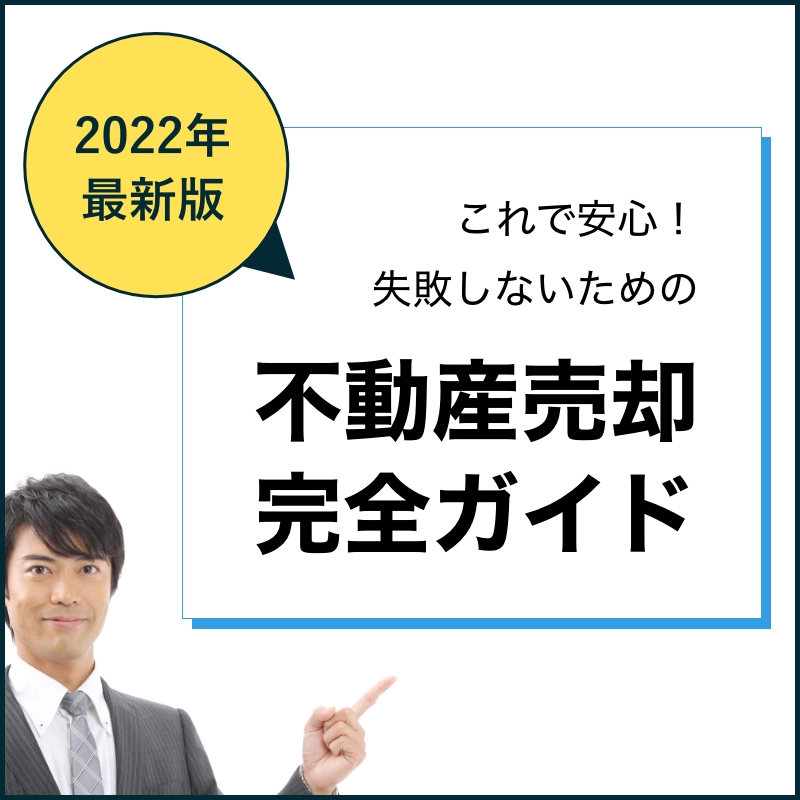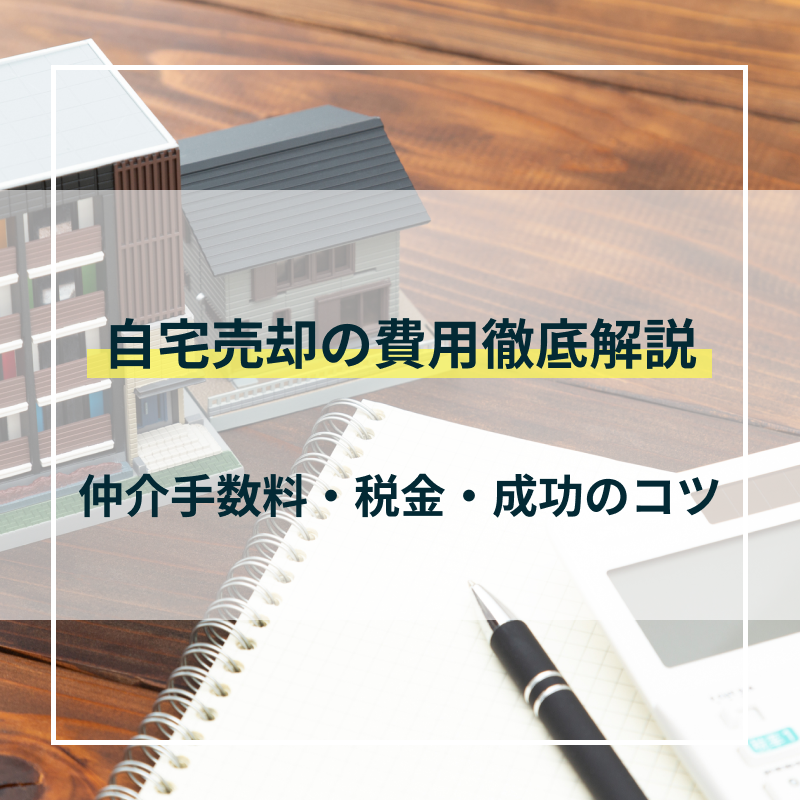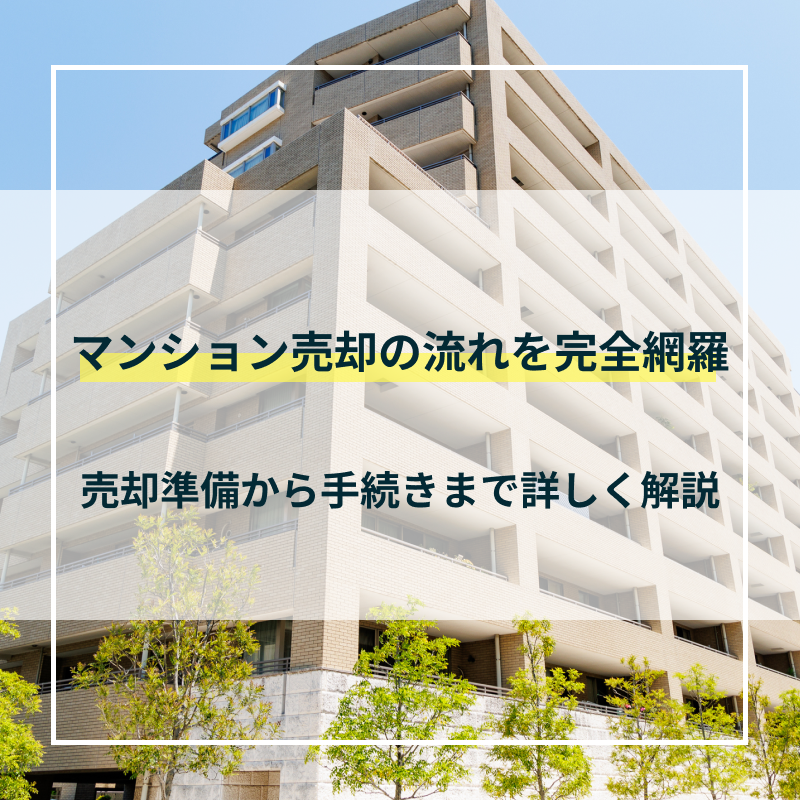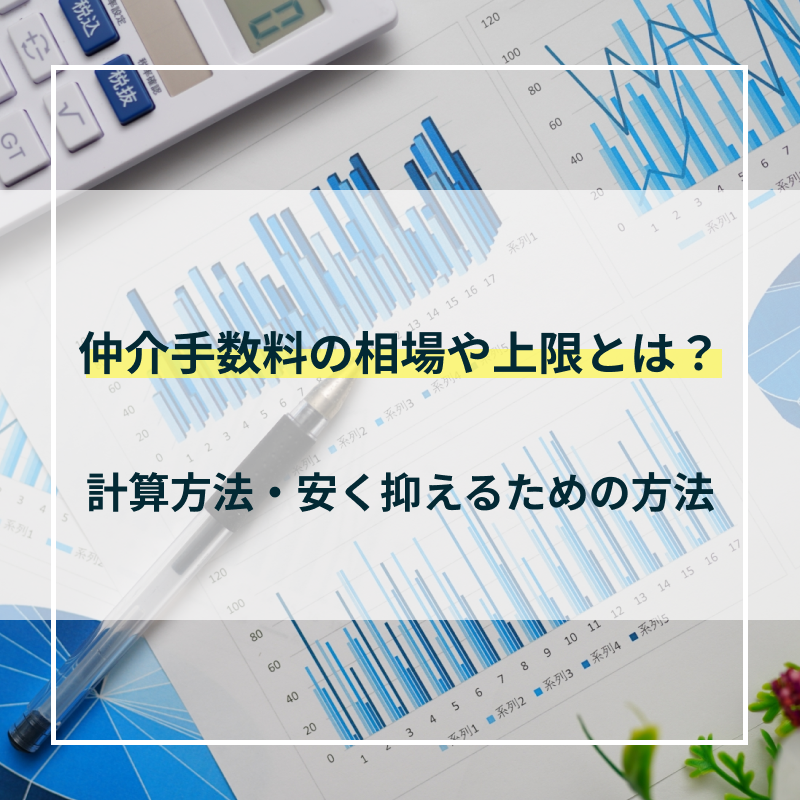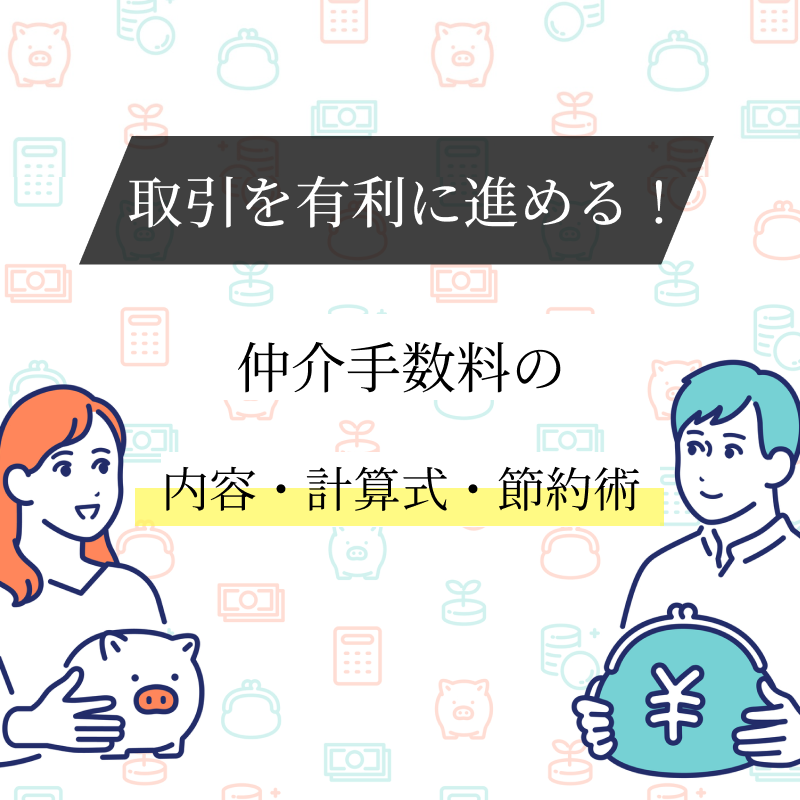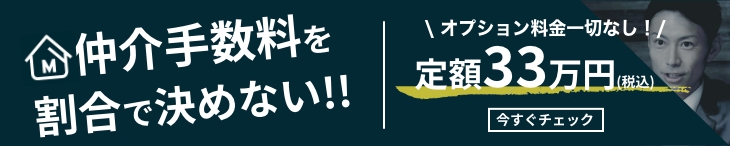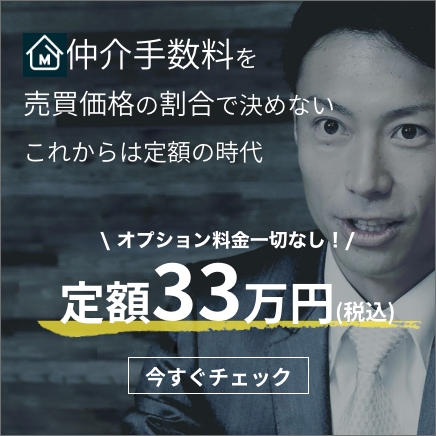
不動産を売却すると、必ずいくつかの税金が発生します。
なかでも売却益が出た場合、一番大きな影響があるのが所得税(譲渡所得・復興特別支援税)と住民税です。
不動産売却で生じた税金には、節税できたり、還付されたり、先送りしたりできる特例があります。
この記事では、不動産を売却するときの税金対策として活用できる特例を7つ紹介します。
この記事を参考にしていただき、ぜひ賢く節税対策するためのヒントにしてください。
- 不動産を売却するときにかかる税金について
- 不動産を売却するときの税金対策・特例7選
不動産の売却でかかる税金は5つ
不動産を売却すると、以下のような5つの税金が発生します。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税(売却益が発生した場合)
- 復興特別所得税(売却益が発生した場合)
- 住民税(売却益が発生した場合)
それぞれいつ・どのようなタイミングで支払う必要があるのか確認していきましょう。
印紙税
印紙税は、契約が成立した場合の売買契約において課税される税金のこと。収入印紙を購入し、契約書に貼付、消印し納付します。
印紙税は契約の金額によって税額が異なるため、次の表で確認しておきましょう。
参考:印紙税の額
| 売買金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万を超えて500万以下 | 2,000円 |
| 500万円を超えて1000万円以下 | 10,000円 |
| 1000万円を超えて5000万円以下 | 20,000円 |
登録免許税
登録免許税とは、売買・相続などによる所有権移転の登記や所有権保存の登記、抵当権の抹消登記など登記申請したときの登記手続きを行う際に納める税金のことです。
登録免許税は課税標準に税率を掛け合わせて求められ、申請する登記の種類ごとに、不動産の価額、債権金額、不動産の個数などによって決まります。
登録免許税は収入印紙で納付しますが、登記手続きを司法書士など専門家に依頼する場合は、登録免許税を含めた額を司法書士事務所へ支払うのが一般的です。
譲渡所得税(売却益が発生した場合)
譲渡所得とは不動産などの資産を譲渡することで生じた所得のことで、譲渡所得に対する税金を譲渡所得税と呼びます。
不動産を売却した金額から取得費用と譲渡費用を差し引いたものが譲渡所得です。
譲渡所得税は、譲渡所得がゼロかマイナスであれば発生しません。
譲渡所得税は「売却する不動産を何年間所有したのか」によって、税率が以下のように異なります。
| 所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% |
復興特別所得税(売却益が発生した場合)
復興特別所得税は、東日本大震災の復興の財源に充てるため、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税です。
納税が義務付けられている期間は2013年1月1日〜2037年12月31日で、所得税に対して2.1%が加算されます。
住民税(売却益が発生した場合)
不動産を売却して利益が出ると、所得税だけでなく住民税も上がります。
いつも納税している住民税とは別に、譲渡所得に応じて課税される住民税が加算されるからです。
住民税は地方税で、譲渡所得が発生した翌年の確定申告後に、以下の方法で納税します。
| 徴収方法 | 対象者 | 納税方法 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 自分で納税する人 (自営業者やフリーランスなど) |
6月ごろ納付書が届き、6月、8月、10月、翌年1月の末日までに コンビニ・銀行振込・電子決済などで納税可能一括納税も可能 |
| 特別徴収 | 給与所得者・年金受給者など | 給与や年金から天引き一括納税は不可 |
オススメ記事
この記事では不動産担保に長年携わってきた経験をもとに、抵当権抹消登記申請書に関して解説ていきます。「不動産を売却する前に抵当権を抹消しておきたい」「ローンは完済しているが抵当権の消し方がわからない」という方のお役に立てれば幸いです。
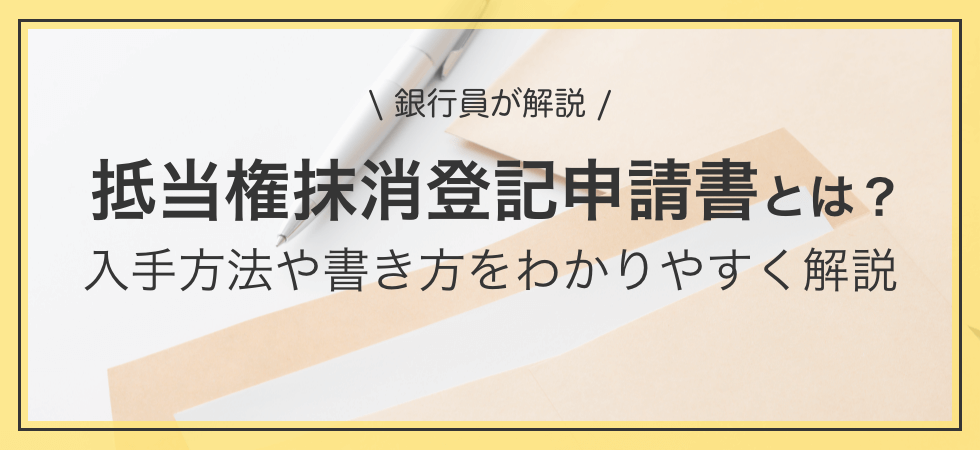
不動産の売却で税金対策できる特例7選
不動産の売却で税金対策できる特例や控除には、おもに以下の7つがあります。
- マイホーム(居住用不動産)を売ったときの特例
- 所有期間が10年を超える不動産を売ったときの特例
- マイホーム(居住用不動産)を買換えたときの特例
- 平成21年及び22年に取得した土地を売ったときの特例
- 相続した空き家を売却したときの特別控除
- 相続物件の取得費加算の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム(居住用不動産)を売ったときの特例
マイホーム(居住用不動産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
特例を利用できる条件
下記の条件を満たす場合は、不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。
また、こちらの特例を利用する場合、住宅ローン控除との併用は不可になりますので注意してください。
[ 1 ] 下記のいずれかを満たすマイホームであること
a. 現在、主に住んでいる自宅である
b. 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
c. かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
d. 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である[ 2 ] 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
[ 3 ] 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
[ 4 ] 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
[ 5 ] 売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
[ 6 ] 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること
特例を利用するための必要書類
3000万円の特別控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を申請する必要があります。
令和3年中に売却したのであれば、令和4年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりませんので、忘れずに申告しましょう。
- 確定申告書・譲渡所得の内訳書
- 戸籍の附票
- 譲渡した土地・建物の全部事項証明書
- 売却時の書類の写し
- 取得時の書類の写し
- 住民票の写しあるいはマイナンバー
所有期間が10年を超える不動産を売ったときの特例
売却物件がマイホームで、所有期間が10年超(売却した年の1月1日において10年を超える)であればこの軽減税率の特例が適用されます。
通常、所有期間が5年超の長期譲渡所得よりも税率が軽減されます。
さらに、この特例は前述した3000万円特別控除と併用できる点が大きなポイントなので、条件に該当すればぜひ利用しましょう!
売却した年の1月1日における不動産の所有期間が10年を超えていれば、3000万円特例控除に加え、控除後の譲渡所得への税率を抑えることが可能です。
譲渡所得の内6000万円以下の部分については通常20%(長期譲渡所得)の税率が14%になります。
この特例の適応対象となる居住用財産(マイホーム)は、個人が有する土地や建物でその年の1月1日における所有期間が10年を超え、さらに次の条件に合致する必要があります。
- 日本国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売ること
- マイホームに住まなくなってから3年以内に売ること
- 売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係にないこと
この特例を利用するためには、確定申告書に次の書類を添えて提出が必要です。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2)売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
詳しくは、下記のサイトを確認してみてください。
マイホーム(居住用不動産)を買換えたときの特例
マイホームを住み替える場合、譲渡所得(売却価格ー{取得費+譲渡費用})が3,000万円を超える場合には居住用不動産の買換え特例を利用する方法もあります。
居住用財産の買換え特例とは、売ったマイホームよりも買ったマイホームの方が高ければ、一定の要件のもと、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができるというもの。
ただし、譲渡益が非課税となるわけではないので注意しましょう。
このように、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得には「3,000万円特別控除」や「特定居住用財産の買換え特例」が適用されますが、併用は認められていません。
また、住宅ローン控除との併用もできませんので注意してください。
特例の対象となるマイホームの詳細の要件は、次のとおりです。
この特例を利用するには、以下の要件を満たすことがわかる書類を添付し、確定申告をすることが必要になります。
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(2)売った年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。
(3)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるものであること。
(4)売却代金が1億円以下であること。
(5)売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。
(6)買い替える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
(7)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。
(8)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。
(9)買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。
(10)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
平成21年及び22年に取得した土地を売ったときの特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得した土地を売却する場合には、1,000万円の特別控除が利用できます。
特例を適用すると、譲渡所得から1,000万円を控除することが可能です。
要件としては、個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものを譲渡したときに適用できます。
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
特例の対象となる不動産の詳細の要件は、下記のとおりです。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
相続した空き家を売却したときの特別控除
相続した空き家を売却したとき、一定の要件を満たしていれば3,000万円の特別控除が受けられます。
マイホームを売却したときに受けられる3,000万円の特別控除と同じです。
対象となる要件はおもに以下のようなものがあります。
- 被相続人の住んでいた家および敷地を売った人が、相続しているか遺贈されていること
- 相続の開始直前まで被相続人が住まいとして利用していた家屋であること
- 相続の開始直前まで被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
他にも細かい要件があるので、相続した不動産を売却する際は、国税庁のサイトを参照してください。
参考:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続物件の取得費加算の特例
相続した物件を一定期間内に売却(譲渡)した場合、相続税のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できます。
適用を受けるための要件は以下の通りです。
- 相続や遺贈によって財産を取得した人であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
参考:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき、「居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」を利用することで税金の還付を受けることができます。
よほど不動産価値が高騰していれば話は別ですが、購入した際に新築だった場合はもちろん、たいていの場合は損失が発生します。これを売却損と呼びます。
売却損が出た場合、不動産を売却した年のその他所得と相殺して所得税や住民税を減らすことができることになっており、これを損益通算と言います。また、損益通算による税負担の軽減は、売却した年に限ったことではありません。
詳細の要件については、下記のとおりです。
この特例を利用するには、以下の要件を満たすことがわかる書類を添付し、確定申告をすることが必要になります。
(1)自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3)災害によって滅失した家屋で当該家屋を引き続き所有していたとしたら、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える家屋の敷地の場合は、その敷地を災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売ること。
(4)譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
(5)マイホームの譲渡価額が上記(4)の住宅ローンの残高を下回っていること。
国税庁:住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
不動産を売却したら賢く税金対策しよう
不動産を売却して譲渡所得が発生すると、翌年の確定申告で税率が決まり課税されます。
さまざまな特例や控除をうまく利用することで、大きな節税効果が期待できます。
特例には一定の要件があるため、この記事を参考にしていただき、賢く節税していただければ幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。