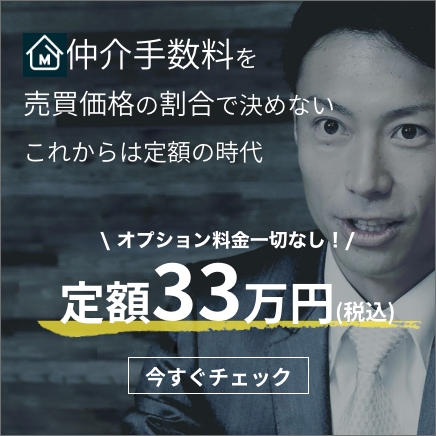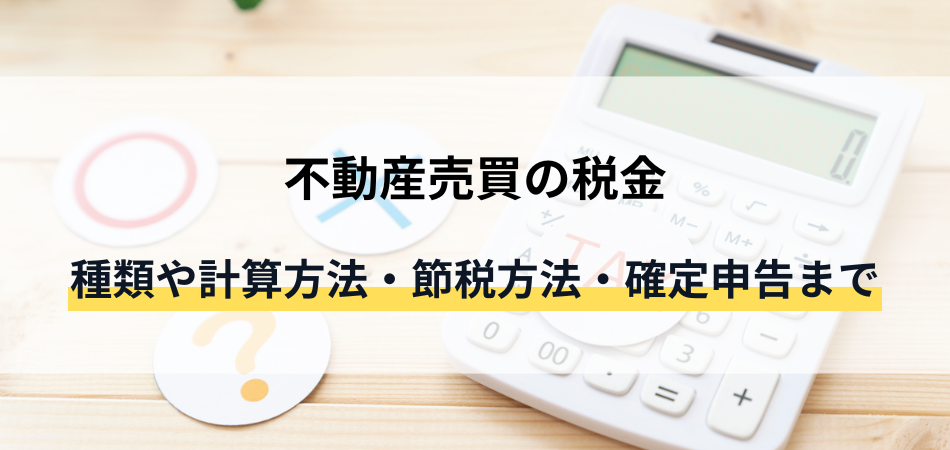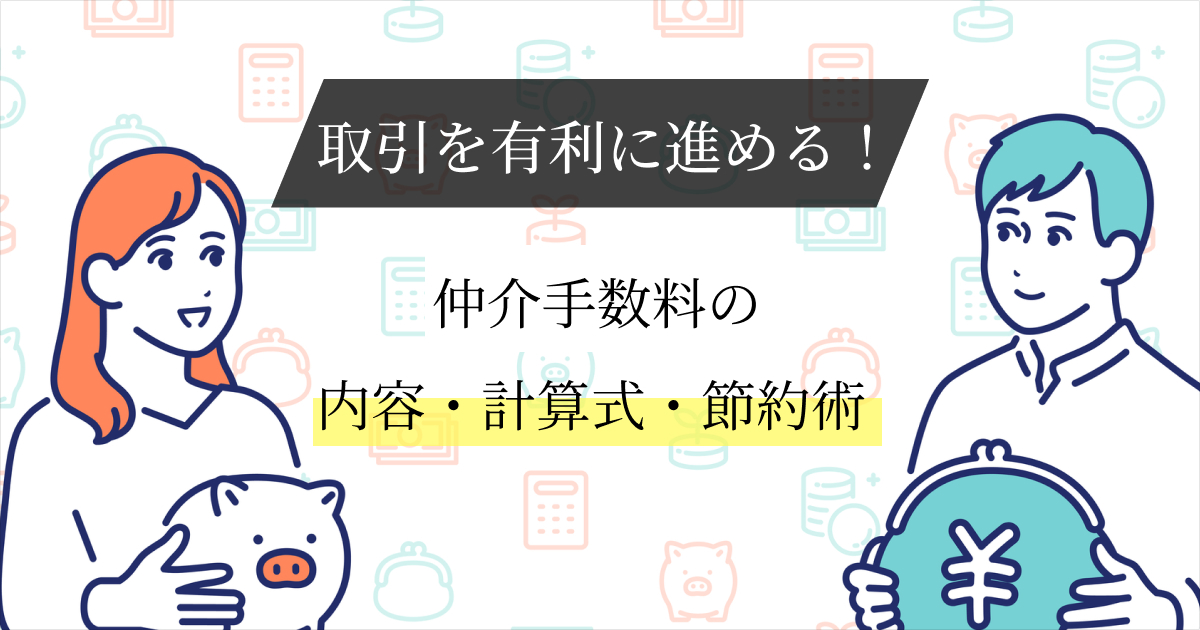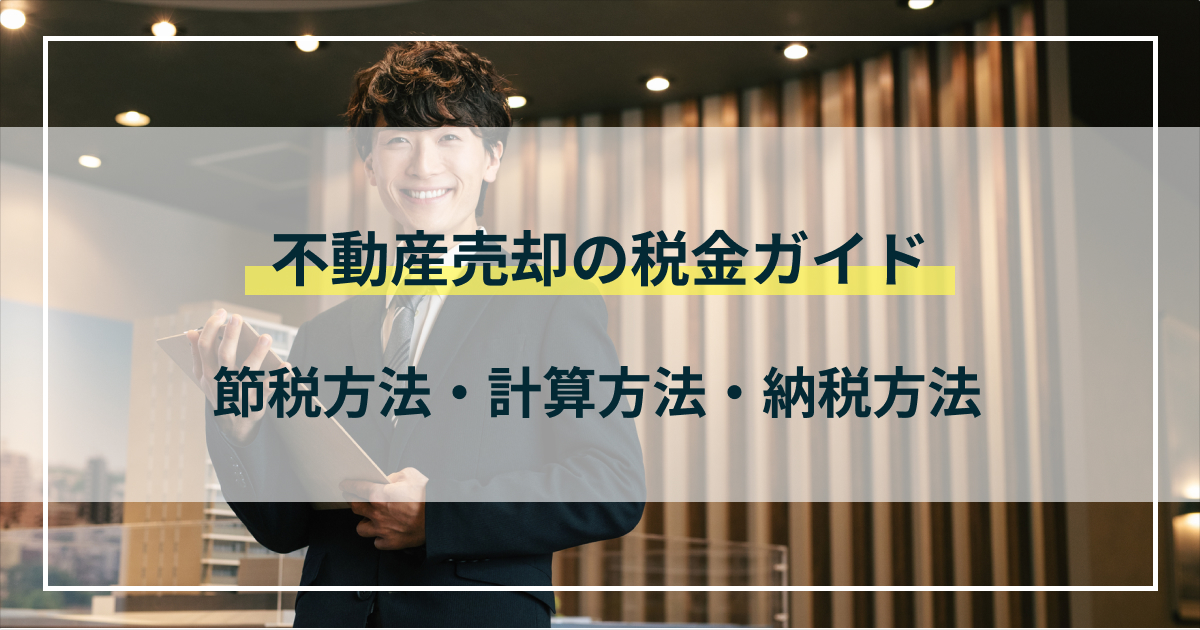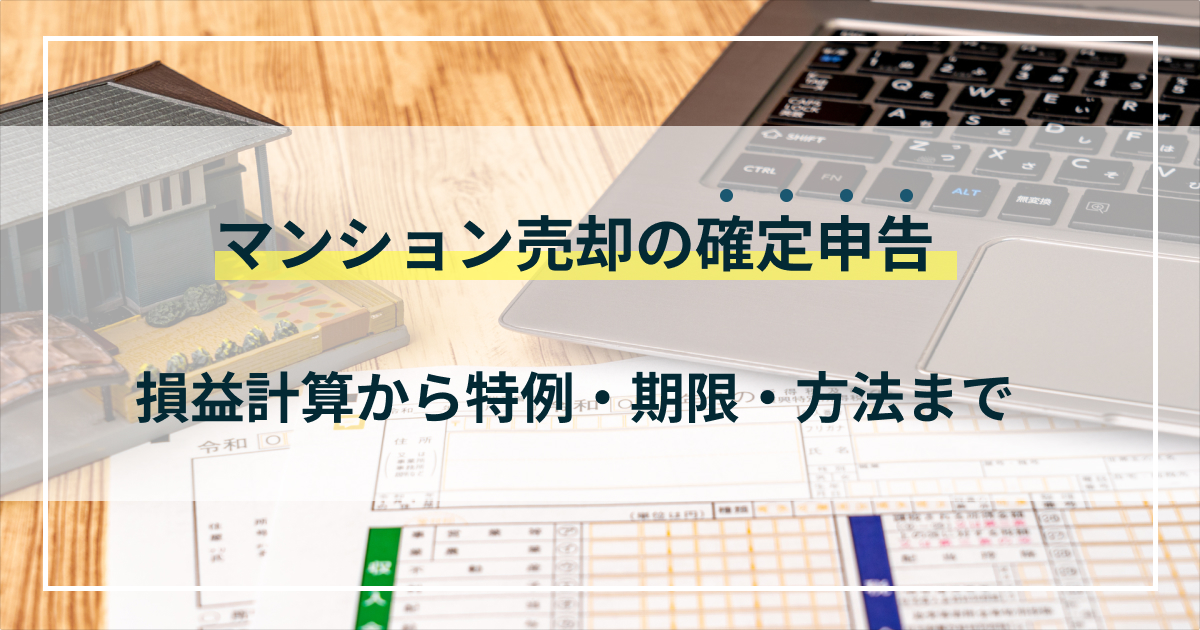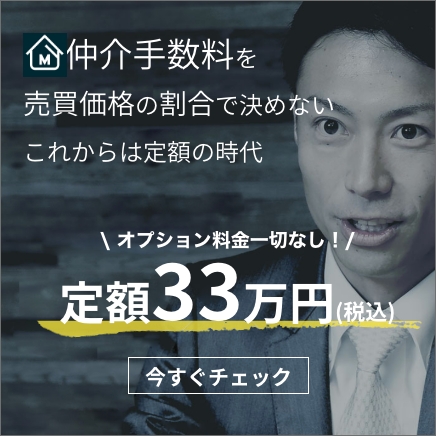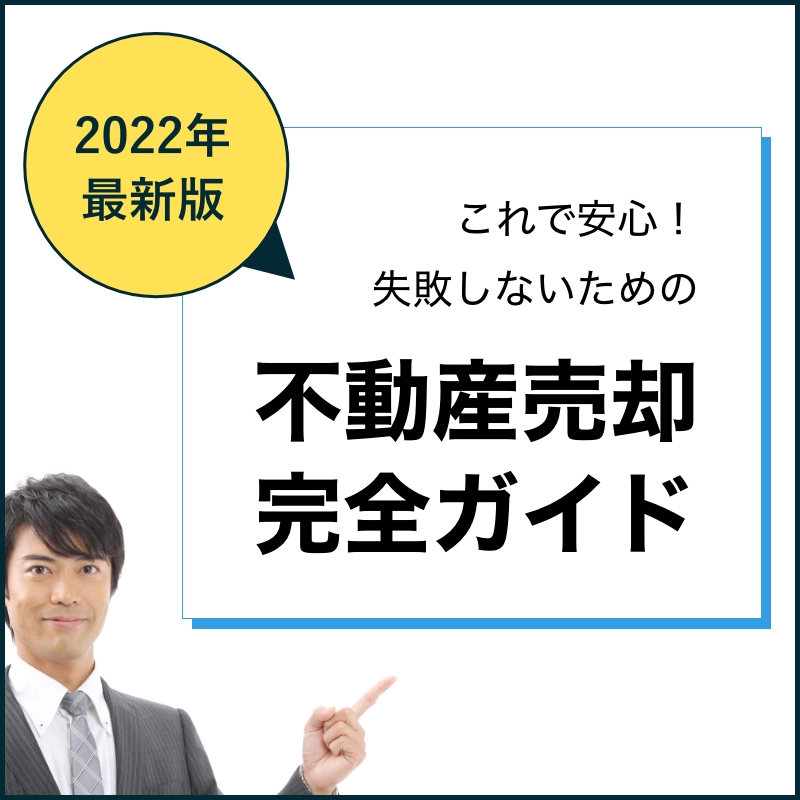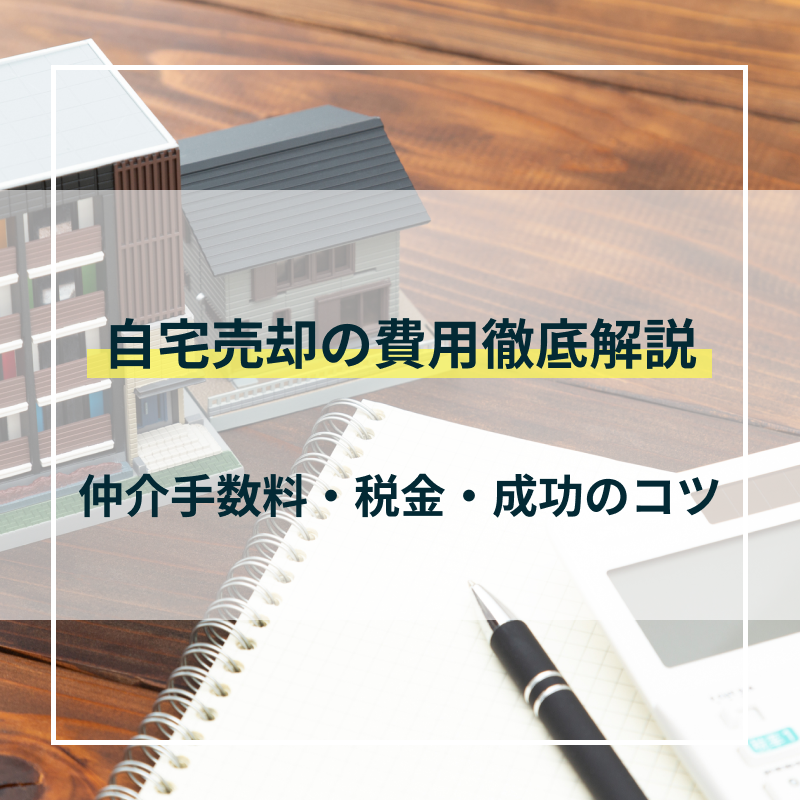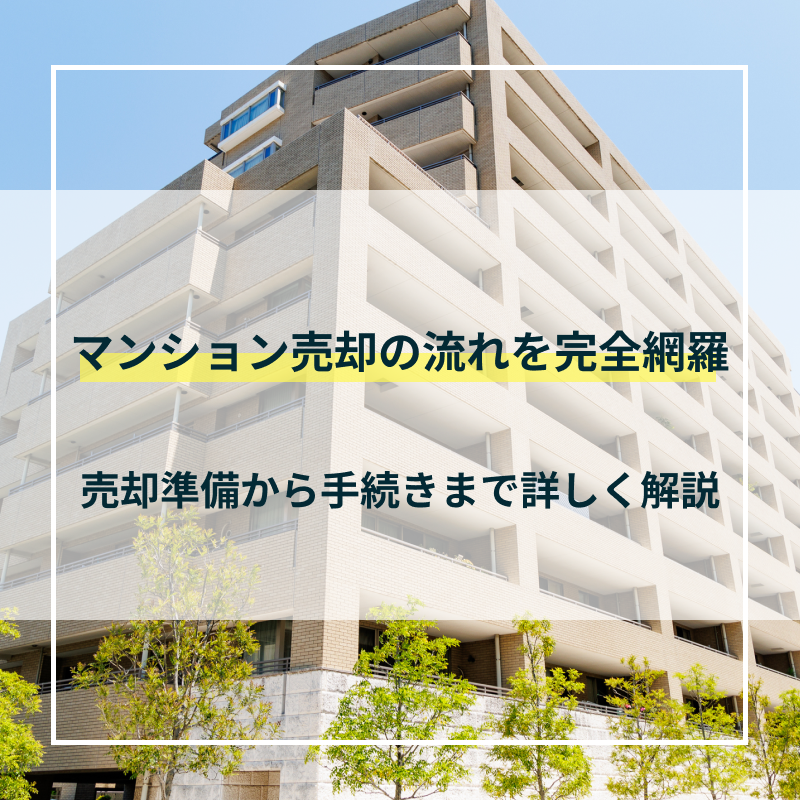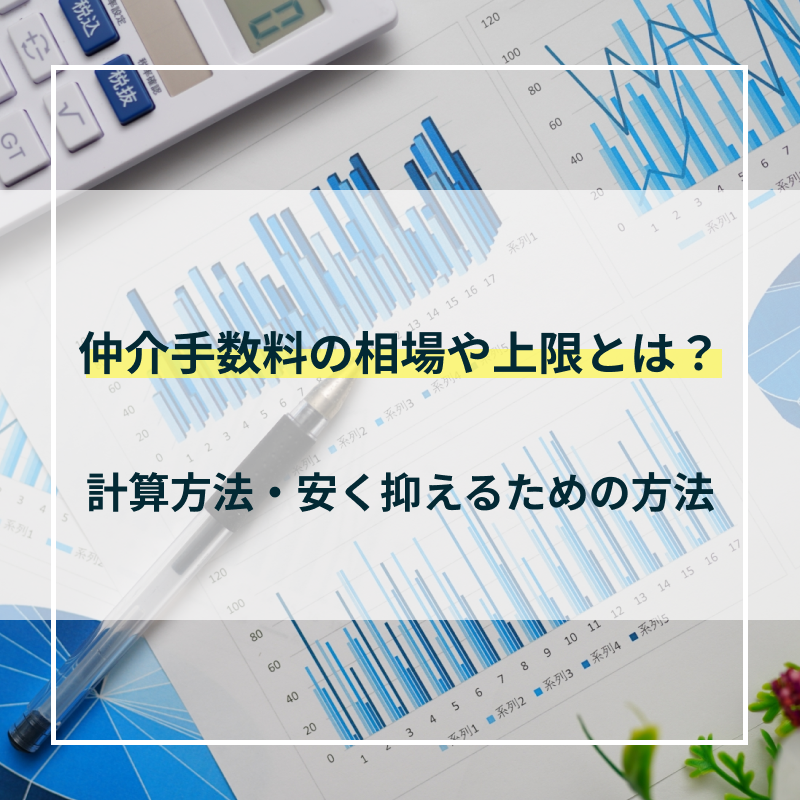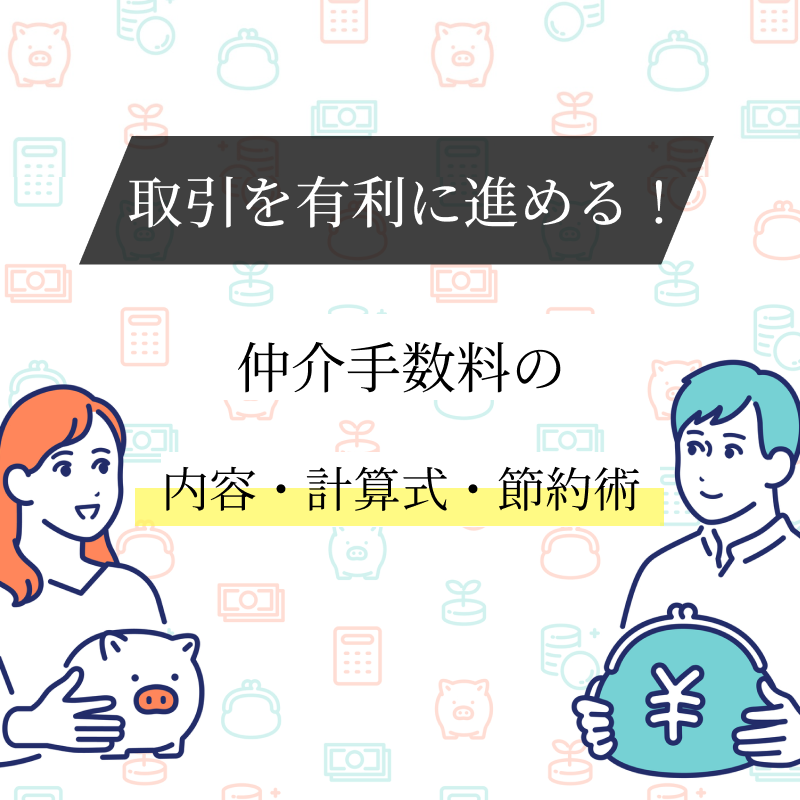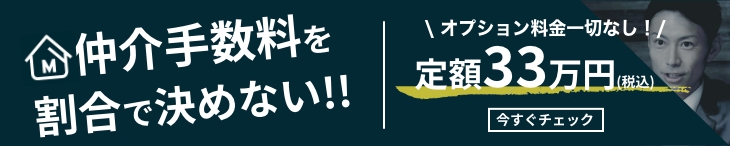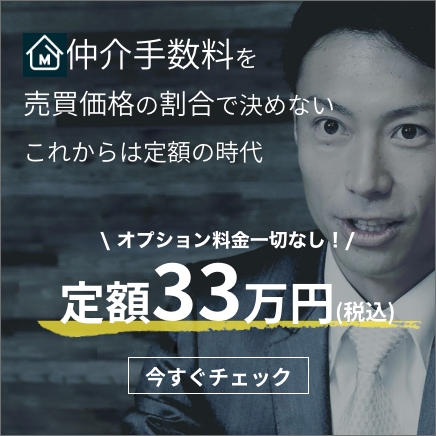
「不動産を売却するとどんな税金がかかるの?」
「不動産売買の際の節税方法を知りたい」
不動産を売買した際の税金について、このような疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却し利益が出た場合、譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税がかかります。
不動産を購入した際にかかる税金は不動産取得税、住民税、印紙税、登録免許税です。
この記事では不動産を売買する際に発生する各税金について、概要、計算方法、節税対策まで詳しく解説します。
この記事を最後まで読んでいただき、ぜひ不動産売買における税金の知識を身につけて、賢い不動産経営に役立ててください。
- 不動産関連でかかる税金の一覧
- 不動産売却後の確定申告について
- 不動産の取得~売却までにかかる税額シュミレーション
不動産の売却でかかる税金
不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金は以下の5つです。
| 税金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 所得税(譲渡所得税・ 復興特別支援税) |
・利益が出た場合にのみかかる税金 ・復興特別支援税は東日本大震災の復興を目的として、2037年まで義務付けられている税金 ・所得税については「不動産を売却したときの譲渡所得と住民税」で詳しく解説します |
| 住民税 | ・いつもの住民税に加えて、譲渡所得があった場合に追加で課税される ・住民税については「不動産を売却したときの譲渡所得と住民税」で詳しく解説します |
| 印紙税※ | ・不動産売買契約書や領収証、融資使用時の金銭消費貸借契約書などの書類に課税される ・印紙税額は課税文書の種類、金額によって異なる |
| 登録免許税※ | ・所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記を申請する際にかかる税金 ・2024年4月からは義務化 |
| 消費税※ | ・仲介手数料に対する消費税 ・仲介手数料によって金額が変わる |
※印紙税・登録免許税・消費税は不動産売却で利益が出なくても課税されます。
不動産の売却でかかる税金
| 税金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 不動産取得税 | ・不動産を取得した翌年にだけ課税される税金 ・不動産取得税に係る税率の特例措置や課税標準の特例措置がある※1 |
| 印紙税 | ・不動産売買契約書や領収証、融資使用時の金銭消費貸借契約書などの書類に課税される ・印紙税額は課税文書の種類、金額によって異なる |
| 登録免許税 | ・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記など不動産の登記を申請する際にかかる税金 ・2024年4月からは義務化 |
| 消費税 | ・仲介手数料に対する消費税 ・例外:土地は非課税・個人間での売買の場合は住宅も非課税 |
おすすめ記事
不動産売却時の税金ガイド|節税対策・計算方法・納税方法を解説
自宅売却時の費用を徹底解説|仲介手数料~税金・成功のコツまで
仲介手数料の相場や上限とは?計算方法・安く抑えるための方法を解説
不動産を売却したときの譲渡所得と住民税
不動産を売却して利益が発生した場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。
不動産所得の計算方法
不動産所得額は「不動産所得額=総収入額-必要経費」で計算可能です。
不動産収入における総収入額には、以下のような収入が対象となります。
- 賃料収入
- 名義書換料、承諾料、更新料や頭金といった名目で受領した金額
- 敷金、保証金などのうち、返還の必要がないもの
- 共益費など名目で受領する電気代や水道代、清掃料など
また、必要経費には以下のような項目があげられます。
- 固定資産税
- 火災保険等の損害保険料
- 修繕費
- 減価償却費
不動産保有中の減価償却
減価償却は、建物や車両などの資産は年数の経過につれて価値が下がっていき、最終的には資産価値が0円になるという考え方です。
そのため、建物や車両といった固定資産の取得にかかった費用の全額を耐用年数に応じて配分して費用計上しています。
新築建物を取得した場合、その後複数年にわたって使用するのが一般的でしょう。
そのため、取得した年に取得費用の全額を経費として計上するのではなく、取得した資産の耐用年数に合わせて少しずつ経費として計上するといった会計上のルールが定められているのです。
では、減価償却費はどのようにして計算するのでしょうか。
新築の木造戸建住宅を1,000万円で購入したケースで考えてみましょう。
木造住宅の法定耐用年数は20年と規定されているため、年間の減価償却費は以下の計算式で算出されます。
(建物価格)1,000万円 ÷(法定耐用年数)20年 =(減価償却費)50万円
上記のように、20年間に分けて経費として計上することになるのです。
サラリーマンは給与所得と損益通算できる?
不動産所得は給与所得と損益通算が可能です。
例えば、給与所得500万円、不動産所得500万円であった場合、合計の所得額は1,000万円となります。
一方、給与所得500万円、不動産所得▲100万円となった場合、合計の所得額は400万円となり、所得額400万円に対して所得税が課税されます。
サラリーマンの方で給与所得額が大きく控除できる費用が少ないといったケースの方も多くいらっしゃるでしょう。
こうしたケースの場合、この仕組みを利用すれば節税対策も可能です。
例えば、軽量鉄骨造建物の場合、建物の主要な骨格材の厚みによって耐用年数が変化します。
具体的には、骨格材の厚さが3mm以下の場合の耐用年数は19年間、骨格材の厚さが3mm以上4mm未満の場合には27年間となります。
仮に同じ金額の建物であった場合には、減価償却期間が短い方が費用計上できる金額が大きくなります。
不動産収入に対する必要経費を増やせるため、状況によっては不動産所得をマイナスで計上でき、納める所得税を抑える効果が期待できるでしょう。
おすすめ記事
【法人向け】経費計上できる費用とは?不動産売却時の仕訳についてケースとともに徹底解説!
相続した不動産を売却するときには遺産分割協議書が必要?作成時の注意点もあわせて解説
相続した不動産を売却したら税務署からお尋ねが届いた!届く理由と対処方法を解説
不動産売却時にかかる税金について
不動産保有時の税金についてご紹介してきました。
では、売却時にはどういった税金がかかってくるのでしょうか。
売却時の税金について知っておかないと、売却後に思わぬ出費となってしまう可能性が考えられます。
そうならないためにも、不動産売却時の税金についてしっかりと理解し、売却計画を立てるのが重要といえるでしょう。
ここでは、不動産売却時にかかる税金の計算方法についてご紹介します。
不動産譲渡所得の計算方法
不動産を売却して得られた利益は「譲渡所得」として課税対象となります。
この際、注意しておきたいのが「売却益=売却価格」とはならない点です。
不動産譲渡所得は「譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費用+譲渡費用)」で計算可能です。
取得費用としては以下の費用などがあげられます。
- 購入代金や建築代金
- 契約書の印紙税
- 取得時に支払った仲介手数料
- 土地の造成費用や測量費用
- 登記費用(登録免許税や司法書士報酬など)
- 不動産取得税
また、不動産の購入価格や取得時の費用が分からない場合には、概算取得費として売却価格×5%にて計上可能です。
どうしても分からない場合には概算取得費で計算するとよいでしょう。
譲渡費用としては、以下の費用が計上できます。
- 売却時の仲介手数料
- 契約書の印紙税
- 建物の解体費用
この他にも、借主がいた場合に立ち退き料を支払った場合には譲渡費用として計上可能です。
以上の情報が分かれば、譲渡所得は簡単に計算できます。
将来的に不動産の売却を考えている場合には、取得費用がすぐ分かるように各種費用の情報を残しておくようにしましょう。
不動産売却における所得税と住民税の確定申告
サラリーマンの場合でも、給与所得以外に不動産の売却で譲渡所得があった場合、確定申告が必要です。
所得税と住民税は一体どのようにして申告すれば良いのでしょうか。
所得税の場合、確定申告手続きを行えば納付税額が分かるため、そのまま手続きを行えば問題ありません。
一方、住民税の場合は、所得税などの確定申告を提出してあれば、確定申告書等のデータが地方公共団体に提供されるため、改めて申告手続きを行う必要はありません。
ここでは、所得税の確定申告についてご紹介します。
確定申告の時期
確定申告は、提出年の前年1月1日から12月31日までの所得額と所得税額を税務署へ申告する手続きです。
確定申告書の提出は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間に行うのが原則となっており、土日や祝日と重なる場合には翌営業日までの受付となります。
尚、2020年と2021年については、新型コロナウイルスの影響から特例的に申告期限延長の対応がなされていました。
2022年についても感染状況によっては延長する可能性もありますが、2021年10月時点では例年通り2月16日から3月15日までの予定となっているようです。
確定申告の方法
確定申告の方法としては、以下の3つの方法があげられます。
- 直接税務署に持参する方法
- 郵送による方法
- インターネット(e-Tax)での申告方法
毎年、確定申告の提出期限間近になると、税務署の窓口も込み合うため、新型コロナ感染防止の観点からもe-Taxや郵送での申告がおすすめといえるでしょう。
確定申告しなかった場合のペナルティ
確定申告を期限までに行わなかった場合、無申告加算税が上乗せされた形で税金を支払いわなくてはなりません。
また、納期限を過ぎてしまった場合、納付が完了するまでの期間に対して延滞税が課されてしまいます。
期限までに確定申告を行うよう気を付けましょう。
不動産取得~売却までの税額シミュレーション
本記事では、不動産に関する税金について詳しくご紹介してきました。
ここでは、年収400万円のサラリーマンが不動産投資をしたケースを想定して、不動産取得から売却までの税額シミュレーションをご紹介しますので見ていきましょう。
物件保有時の所得税・住民税の計算
年収400万円のサラリーマンの場合、国税庁の公表する計算式にあてはめると給与所得控除の計算式は次の通りです。
「400万円 × 20% + 44万円 = 124万円」
この給与所得控除を用いて給与所得額を求めると次のようになります。
「400万円 - 124万円(給与所得控除)= 276万円」
一方で、不動産所得は次のように求められます。
「(不動産収入額)300万円-(必要経費)250万円=50万円」
「(給与所得)276万円+50万円=326万円」
ここから基礎控除や社会保険料控除などの所得控除が100万円だとすると、課税所得金額は次の式で求められます。
「(不動産所得)326万円-100万円=226万円」
課税所得金額226万円の場合に適用される所得税率は10%です。
この数字を適用すると所得税額は次の式になります。
「(課税所得金額)226万円×(所得税率)10%-97,500円=128,500円」
住民税は「所得割分10%+均等割分」が課税されるため、住民税額は次の式になります。
「226万円×(所得割分)10%+(均等割り分)5,000=231,000万円」
物件売却時の譲渡所得税の計算
築20年のRC造賃貸マンションを10年後に売却した場合、譲渡所得税はいくらになるでしょうか。
購入価格5,000万円(土地1500万円・建物3500万円)に対して、10年後に4,000万円で売却できたと仮定した場合でシミュレーションしてみましょう。
まず、取得費は次の式で求められます。
「(建物価格)3,500万円―(減価償却)2,079万円 + (概算取得費)200万円(売却価格の5%)= 1,621万円」
譲渡費用を仲介手数料、契約書印紙代などを考慮して150万円とすると譲渡所得額は次の通りです。
「(売却価格)4,000万円 ―(取得費1,621万円+譲渡費用150万円)= 2,229万円」
所有期間10年の場合、長期譲渡所得となるため、税率20.315%が適用され、譲渡所得税額は次の計算式で算出することができます。
「(譲渡所得額)2,229万円× (税率)20.315%= 452.8万円」
おすすめ記事
仲介手数料の勘定科目とは?詳しい仕訳方法をケースごとに徹底解説!
最新版!不動産取得税|軽減措置の税率・要件・申請方法などを完全解説
取得費不明ならコレ!権利証なし、譲渡所得計算にお困りな方へ対応策を解説
まとめ
本記事では、不動産売買に関する税金についてご紹介してきました。
不動産投資を検討するのであれば、不動産関連の税金について理解しなくてはなりません。
不動産に関する税知識が身に付けられれば、自身の資産形成に大きく役立てられます。
また、不動産に関する税知識を深めるには、実際に物件の取得するのが一番の近道といえるでしょう。
本記事を参考にして、早速不動産投資を始めてみてはいかがでしょうか。