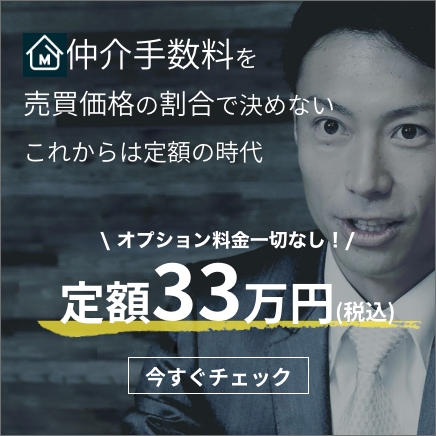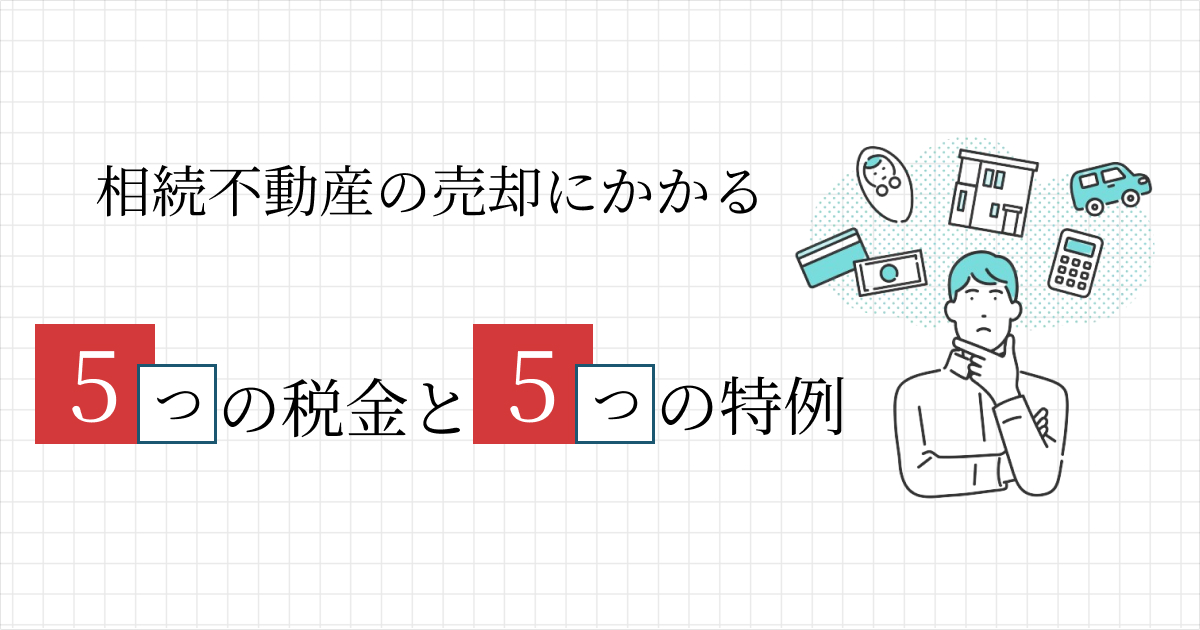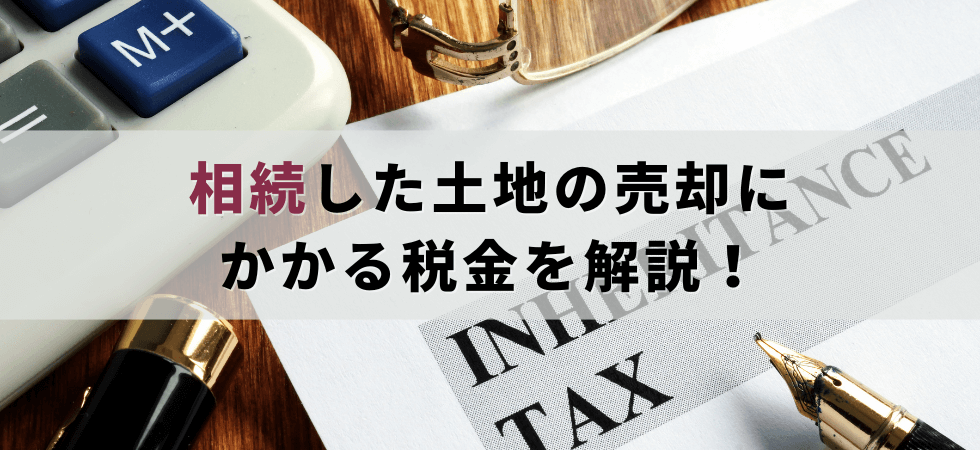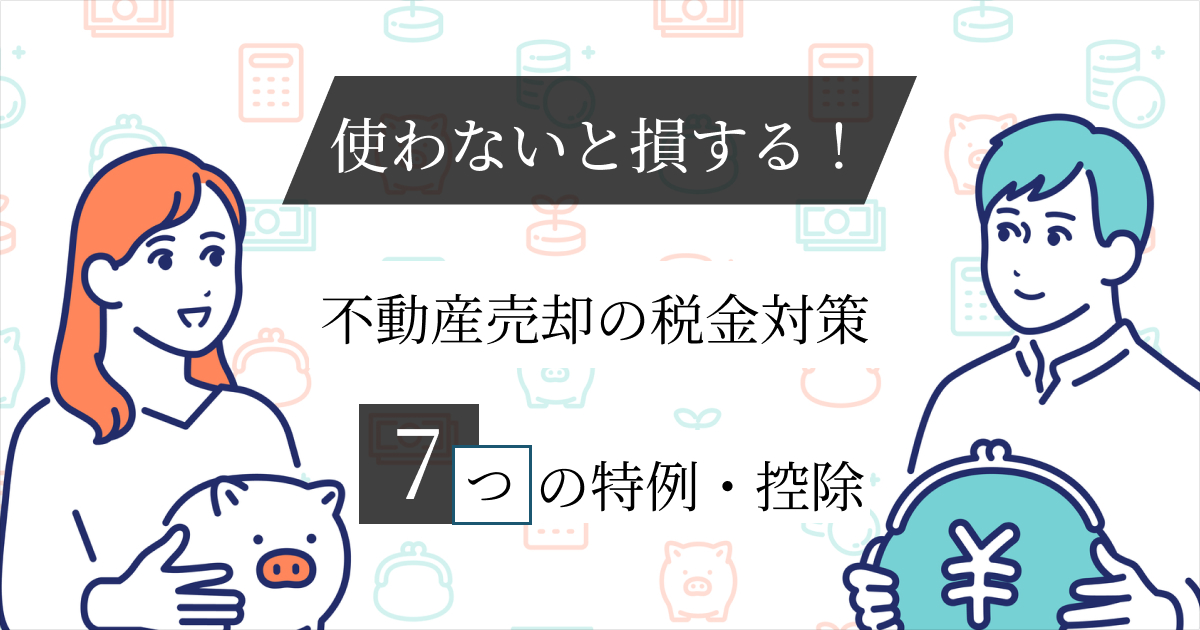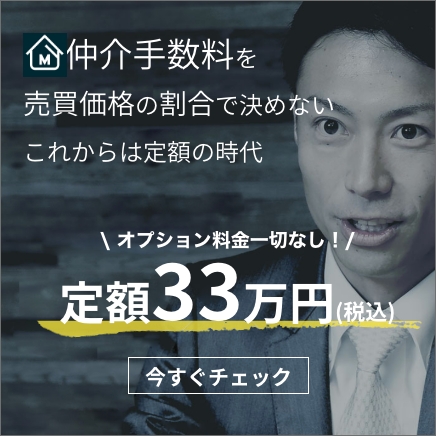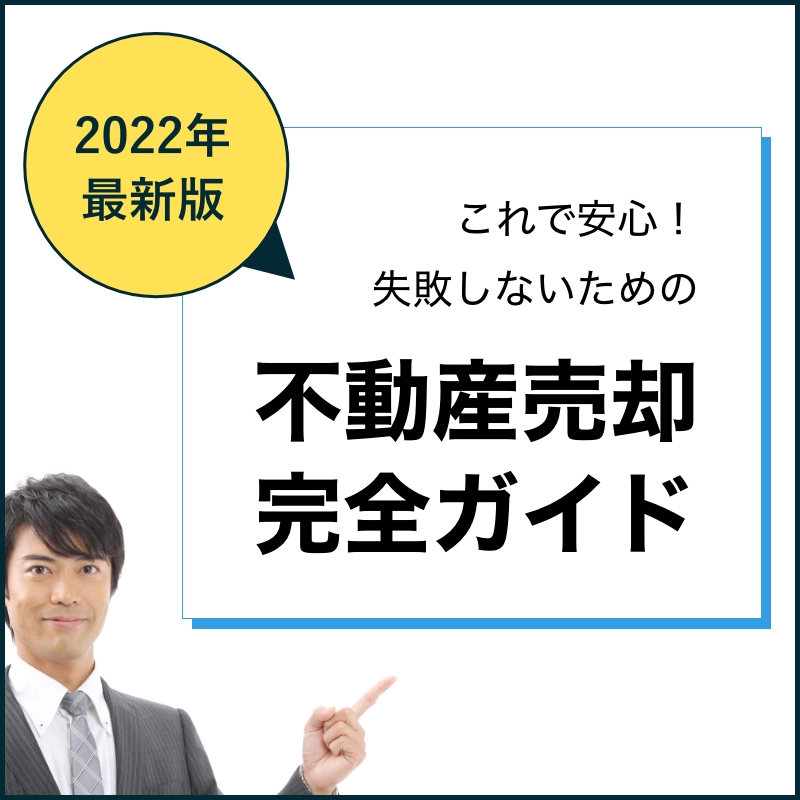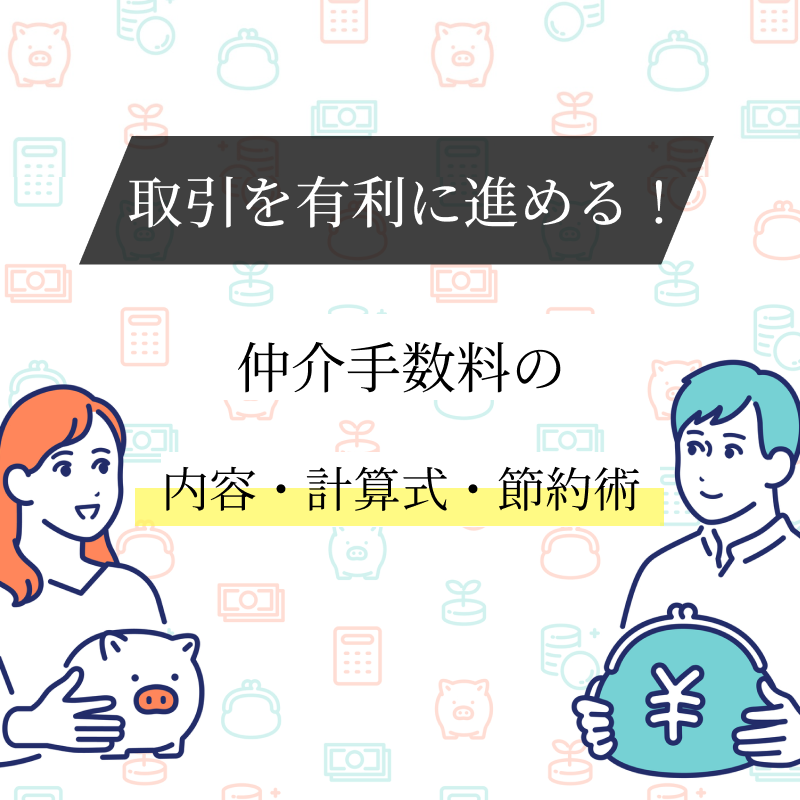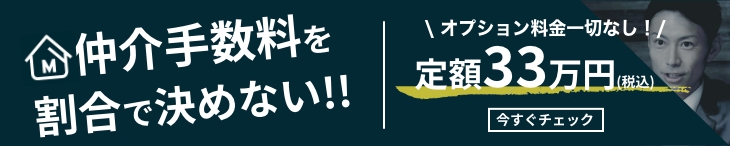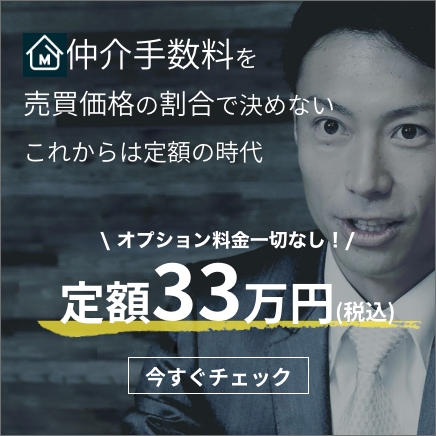
相続した不動産の売却では、特に税金の疑問や悩みを持つ方も多いでしょう。
本記事では、相続した不動産の売却にかかる税金について、相続物件を売却する際に生じる5つの税金と、それらを軽減できる5つの特例について詳しく解説します。
相続税や譲渡所得税、復興特別所得税など、さまざまな税金が適用されることがありますが、適切な特例を利用すれば大きな節税効果が見込めます。
この記事を最後まで読むことで、相続不動産の売却にまつわる税金とその対策について知識を深めていただき、理想の形で不動産の売却をすすめましょう。
相続した不動産を売却した際かかる5つの税金
不動産を相続した際にかかる税金は、以下の5つです。
- 相続税(相続税の基礎控除を超えた場合)
- 登録免許税
- 譲渡所得税(所得税と住民税・売却益が出た場合)
- 復興特別所得税(売却益が出た場合)
- 印紙税
相続税(遺産にかかる基礎控除を超えた場合)
相続した不動産が遺産にかかる基礎控除を超えた場合に課税されるのが相続税です。
相続税には、課税価格から一定額を控除する制度があります。この「遺産に係る基礎控除額」は下記で計算できます。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
例えば、相続人が妻と子供1人の場合、3,000万円+600万円×2名=4,200万円という計算になり、4,200万円が「課税遺産総額」から控除され、この基礎控除額を超える相続財産がある場合に相続税が発生します。
登録免許税
不動産の所有者については、法務局が管理する登記簿に記載があり、売買等で所有者が変更すると、所有者変更の手続きをします。相続も同様に所有者変更の登記を申請する必要があります。
そして、この変更登記を申請する時に発生する税金が、登録免許税です。登録免許税の計算式は下記の通りです。
登録免許税額 = 土地と建物の固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額は、所有者に送付される「課税明細書」、または、役所で取得できる「固定資産評価証明書」で確認することができます。
なお、固定資産税評価額は土地と建物、それぞれ別々に定められており、その両方に登録免許税がかかります。
譲渡所得税(所得税と住民税・売却益が出た場合)
不動産の売却により利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
不動産売却時にかかる税金を「譲渡所得税」といいますが、正式には「所得税」と「住民税」のことです。譲渡所得の計算は下記の通りです。
不動産の譲渡所得 = 譲渡収入金額 ‐(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得税は所有年数によって、税率が以下のように異なります。
| 所得税率 | 住民税率 | 合計の税率 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年未満の場合) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超の場合) | 15.315% | 5% | 20.315% |
相続した不動産は被相続人が相続した日から計算され、所有年数の判断基準は売却した年の1月1日時点となるので注意が必要です。
復興特別所得税(売却益が出た場合)
復興特別所得税は、2013年から課税が始まった税金で、所得税を納めるすべての個人が対象です。
給与所得のある会社員でしたら、自動的に天引きされています。
不動産の売却においては、必ずしも発生するわけではなく、譲渡所得税と同じく課税対象となる譲渡所得がマイナスの場合は発生しません。
復興特別所得税は、2段階の計算で算出します。
まず、譲渡所得に、短期譲渡、もしくは、長期譲渡の税率をかけて基準所得税額を算出します。
次に、復興特別所得税率をかけますが、特別所得税の課税額を計算する場合は、税率は一律2.15%で計算します。
この税率は一律で、課税対象金額や所有条件等に影響されず、納税者の所得額等も関係ありません。
印紙税(売買契約書に貼付)
通常、不動産を売却する際は、不動産会社が仲介に入り、契約書を作成して売買契約を締結します。
売買契約書には、売買価格に応じた印紙を貼付することが税法で定められています。
例えば、不動産の価格が5,000万円の場合は10,000円の印紙を、1億円の場合は30,000円の印紙を貼付します。
相続した不動産の売却で節税できる5つの特例
相続した不動産の売却で節税できる特例には、以下の5つがあります。
- 取得費加算の特例
- 居住用不動産の3,000万控除の特例(同居していた場合)
- 相続した空き家売却の3,000万控除の特例
- 所有期間10年超の不動産に対する軽減税率
- 特定居住用財産の買換え特例
取得費加算の特例
被相続人が亡くなった日から3年10カ月以内に相続した財産を売却した場合に使える所得税があります。譲渡所得から財産を取得した時の費用をマイナスし、譲渡所得を軽減できます。
遺贈では適用されますが、生前贈与では原則、適用されないのでご注意ください。
3,000万円控除や買換え特例との併用可能です。
- 相続で取得した財産であること
- 相続税を支払った人であること
- 確定申告をすること
- 相続財産を相続を開始した日の翌日から相続税の申告期日の翌日以降3年を経過する日までに売却していること
居住用不動産の3,000万控除の特例
居住用の不動産、いわゆるマイホームを相続し売却する場合に適用される特例です。被相続人と同居している相続人が不動産を相続した後に売却する場面で利用しやすいでしょう。
文字通り、不動産を売却して得た譲渡所得から3,000万円が控除されるので、譲渡所得が3,000万円以下であれば、所得税は発生しません。
- 現在、自らが居住している家屋であること(マイホーム)
- 住まなくなってから3年を経過する日の年の12月31日までに売却すること
- 住まなくなってから家屋を取り壊した場合、転居後、3年後の12月31日までか、取り壊した後の1年以内か、いずれかの早い日までに売却すること
相続した空き家売却の3,000万控除の特例
空き家問題対策の一環として設けられた特例です。
現在、木造戸建ての空き家が増加しており、地震時の倒壊や防犯上の問題が指摘されています。
国はこのような空き家を減らす目的で、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定、翌2016年には、相続で発生した空き家の流通を後押しするため「相続空き家の3000万円特別控除」を制定しました。
このような制度の趣旨から、「区分マンション」と、旧耐震基準である「1981年5月31日以前に建築された家屋」は除外されています。
なお、建物を解体し土地として売却する場合も一定の条件を満たせば適用されます。
- 相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋であること
- 区分所有建物(マンション等)以外の家屋であること
- 1981年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続の開始直前まで被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
- 相続の時から譲渡の時まで賃貸していないこと
参考:国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
所有期間10年超の不動産に対する軽減税率
所有期間10年を超えた不動産を売却する時に使える軽減税率です。
10年以上所有している不動産を売却する際には、ぜひ活用したい特例です。
3,000万特別控除と併用することもできます。
この軽減税率は、譲渡所得税が発生する場合、大きなメリットがあります。
譲渡所得が6,000万円を超える場合、6,000万円以上と以下で税率が変わり、通常、譲渡所得税や住民税などを合わせると約20%のの税率が、特例の適用で約14%にまで税率が下げられます。
| 譲渡所得の金額 | 6,000万円以下の部分 | 6,000万円超の部分 |
|---|---|---|
| 所得税 | 10.21% | 15.315% |
| 住民税 | 4% | 5% |
| 合計の税率 | 14.21% | 20.315% |
- 譲渡した年の1月1日において、家屋と土地の所有期間が10年を超えていること
- 親族以外の第三者に譲渡すること
- 住んでいる住宅か、居住をやめてから3年以内の家屋であること
- 過去3年の間に所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例を受けていないこと
- 過去3年の間に3,000万円特別控除の特例を受けていないこと
- 住まなくなった日の3年後の12月31日までに売却すること
特定居住用財産の買換え特例
大前提として、買換え特例は、税金を繰り延べる(先延ばしにする)制度です。
買換え特例の場合、買換え後の不動産を売却する時に税金が安くなるのではなく、課税が発生するという納税期限の繰り延べられます。
買換えでは譲渡所得税等に対する課税がなく、買換え後の住宅を売却する時に、課税されるというわけです。
また、適用されるためには、現在所有している不動産とこれから取得する不動産の両方が条件を満たしていなければなりません。
なお、3,000万円控除とは併用不可ですので、ご注意ください。
- 居住用不動産で所有期間が10年以上、居住期間が10年以上であること
- 売却価格が1億円以下であること
- 前年の1月1日から譲渡した年の翌年の12月31日までの間に買換えること
- 取得する個人が居住する土地家屋であること(借地権含む)
- 住宅家屋の床面積は50㎡以上、土地の面積は500㎡以下であること
- 中古住宅の場合は、一定の耐震基準(新耐震基準)を満たしていること
- 耐火建築物でない場合は、建築後年数が25年以内であるか、一定期間内に新耐震基準を満たしていることを証明すること
相続した不動産の売却後の確定申告が必要なケース
相続した不動産の売却後、確定申告が必要かどうかはケースによって異なります。
この章では、以下の3つのケースについて解説します。
- 譲渡所得が0円またはマイナスなら確定申告は原則不要
- 譲渡所得が発生したら確定申告は必要
- 譲渡所得が3,000万円以下で特例を使うなら確定申告は必要
譲渡所得が0円またはマイナスなら確定申告は原則不要
譲渡所得が0円またはマイナスなら、原則的に確定申告の必要はありません。
ただし、給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、確定申告が必要です。
相続した不動産をマイホームとして利用した後に売却してマイナスが出た場合、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算できる特例があります。
マイホームとして利用していた場合、この特例を利用するために確定申告した方が有利です。
参考:国土交通省|№1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
譲渡所得が発生したら確定申告は必要
譲渡所得が発生したら確定申告は必要です。
確定申告しないと加算税や延滞税などが加算され、悪意があったとみなされる場合は重加算税が課せられます。
特例を利用すれば税金は発生しないか軽減できるので、譲渡所得のあった翌年の3月15日までに確定申告しましょう。
譲渡所得が3,000万円以下で特例を使うなら確定申告は必要
先に紹介した「居住用不動産の3,000万控除の特例(同居していた場合)」や「相続した空き家売却の3,000万控除の特例」を利用する場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得がわずかでも発生した場合、確定申告は必要ですし、特例を利用することで譲渡所得税が課税されなかったり軽減されたりします。
オススメ記事
相続した不動産を売却したら税務署からお尋ねが届いた!届く理由と対処方法を解説
この記事では不動産売却後に届くことのある「お尋ね」という封書について詳しく解説していきます。税務署からの書類ということもあり、不安に感じてしまう方もいらっしゃると思いますので、万が一の時のためにも基本的な知識をつけて準備しておきましょう。
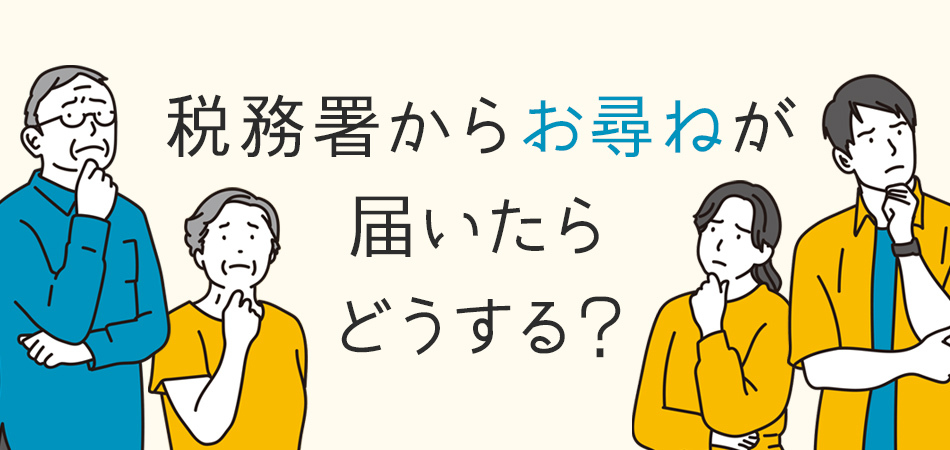
相続した不動産の放置はリスキー
相続した不動産を売却すると、翌年の確定申告と納税が必要になります。
しかし、売却益が発生しても特例をうまく活用すれば節税が可能です。
不動産を放置しているとさまざまなリスクが発生します。
そのまま所有し続けると年々不動産としての価値は下がり、維持費や固定資産税など経費ばかりがかさむことになりかねません。
相続した不動産は、なるべく早めにプロに相談して適切な形で売却するのが得策です。
この記事を参考にしていただき、相続した不動産をスムーズに売却し、賢く節税するヒントにしていただければ幸いです。