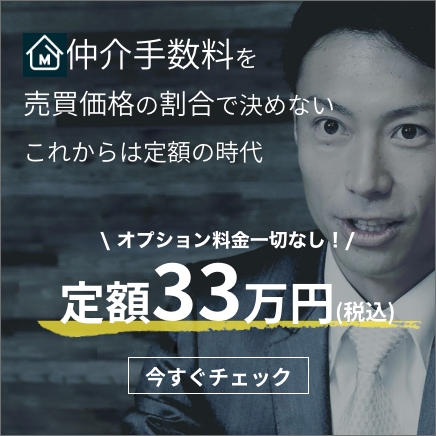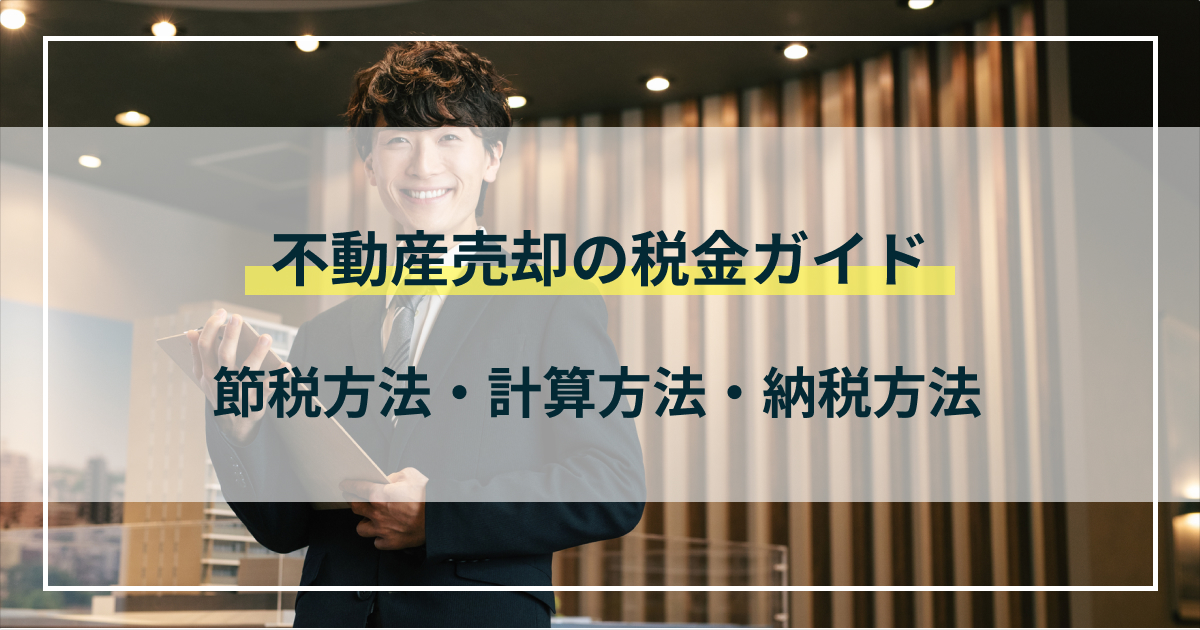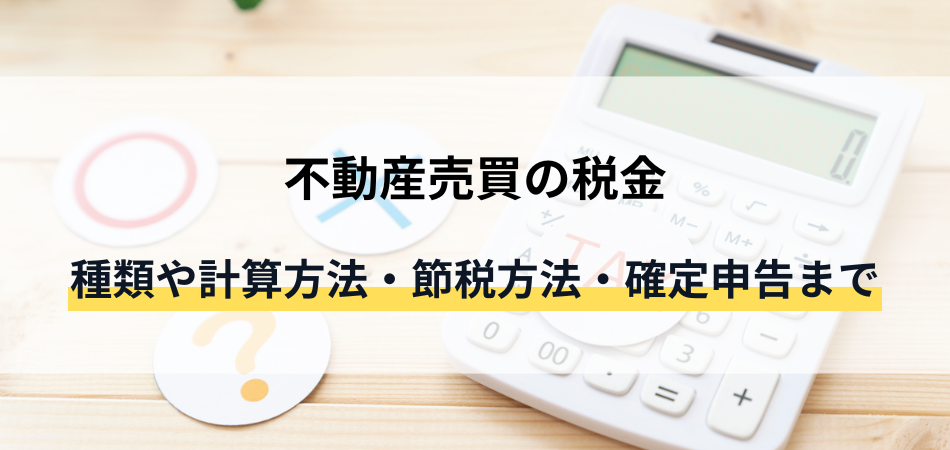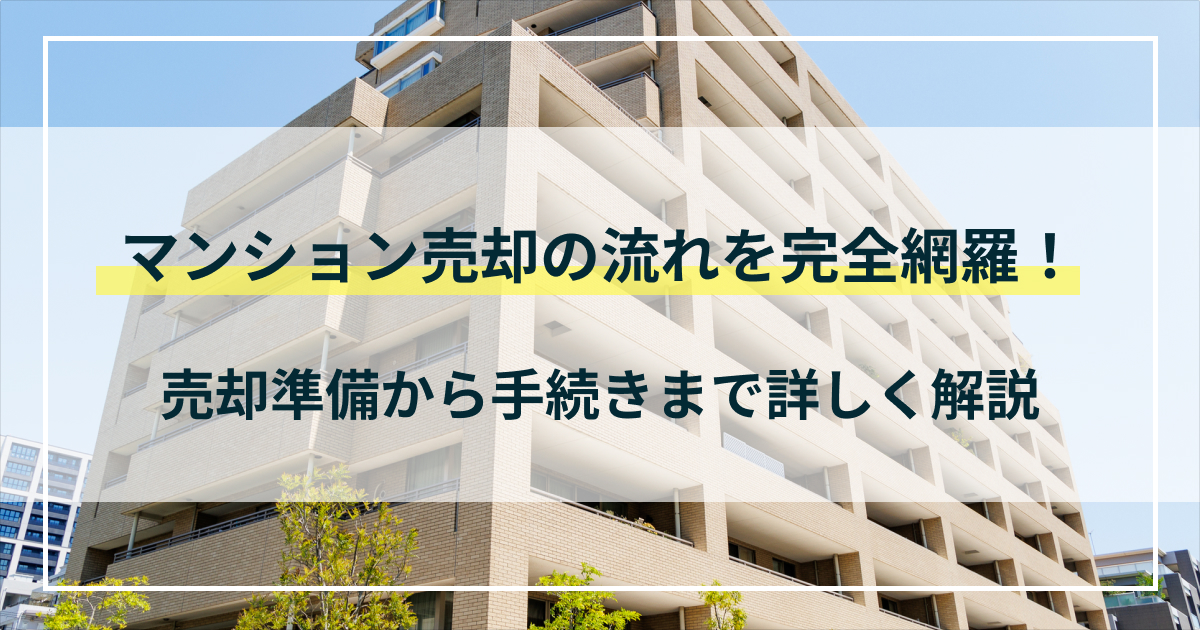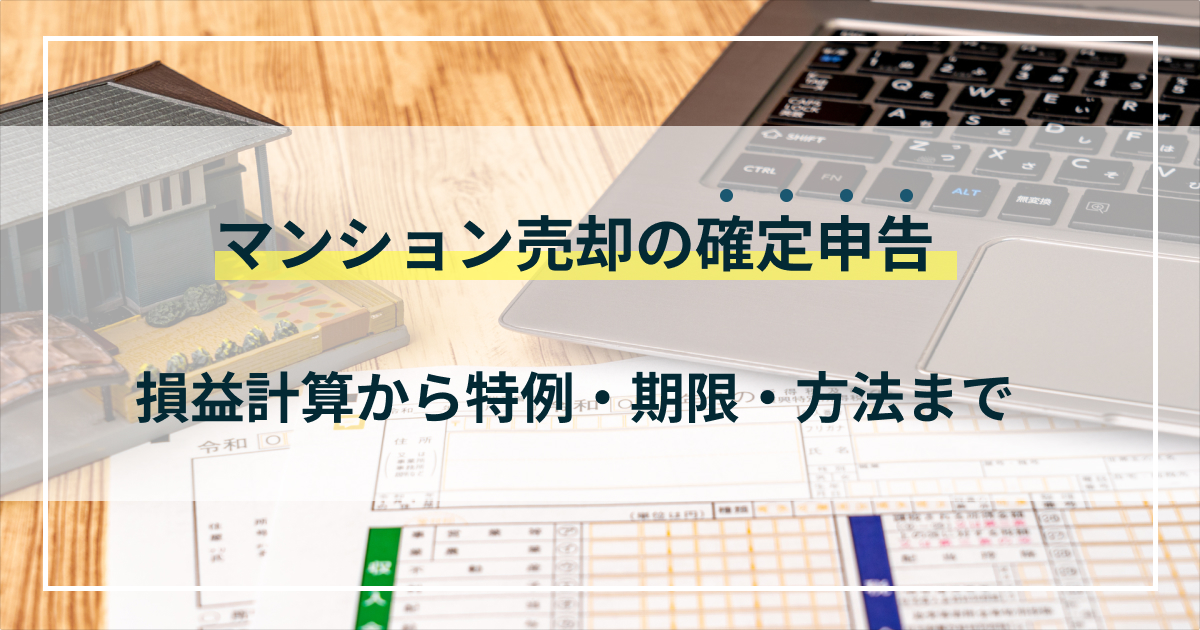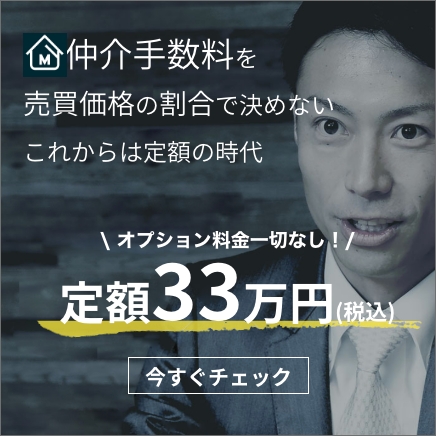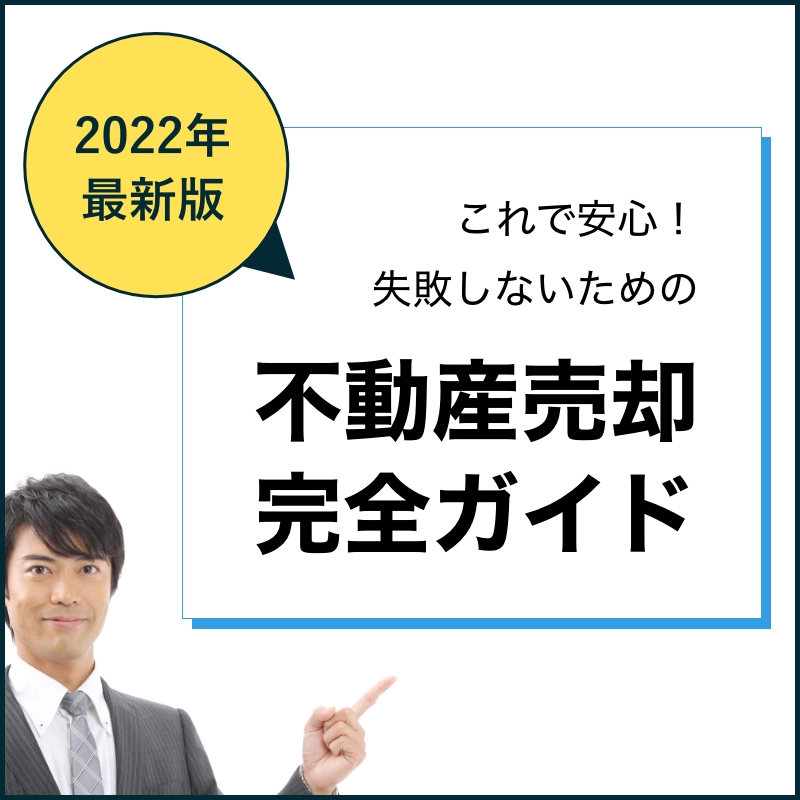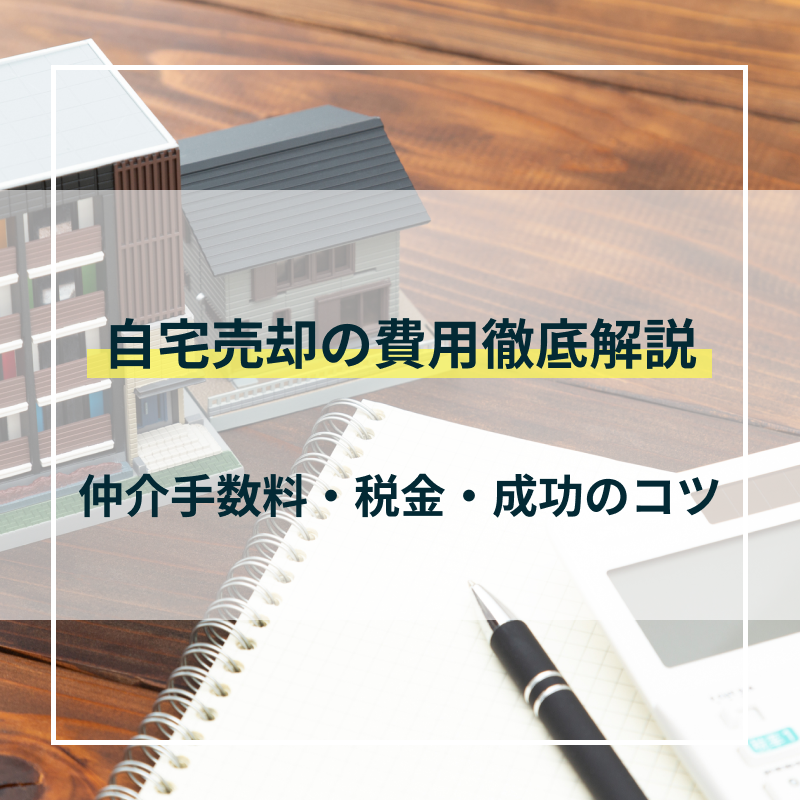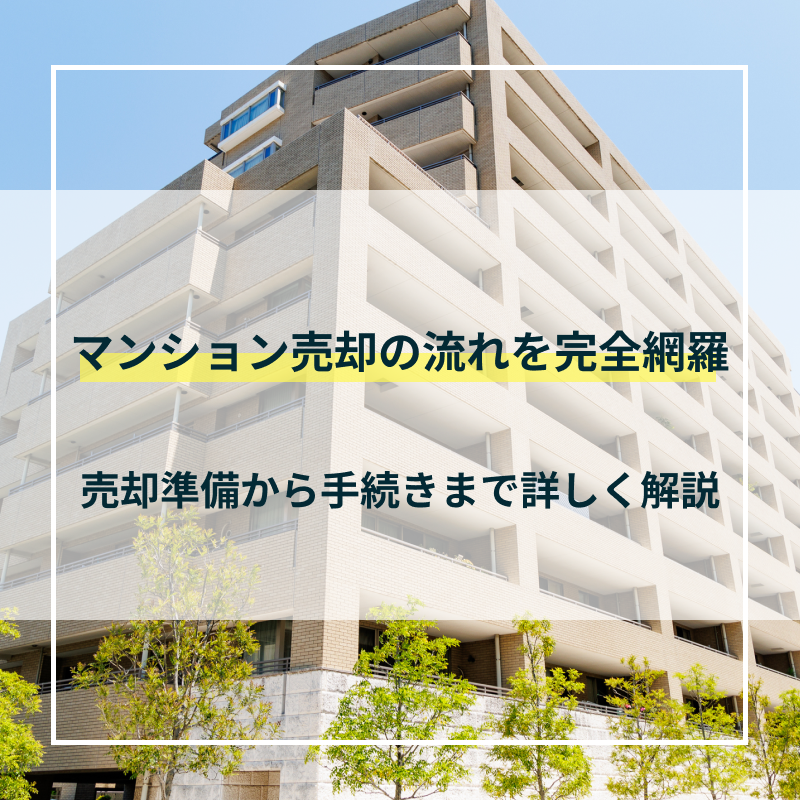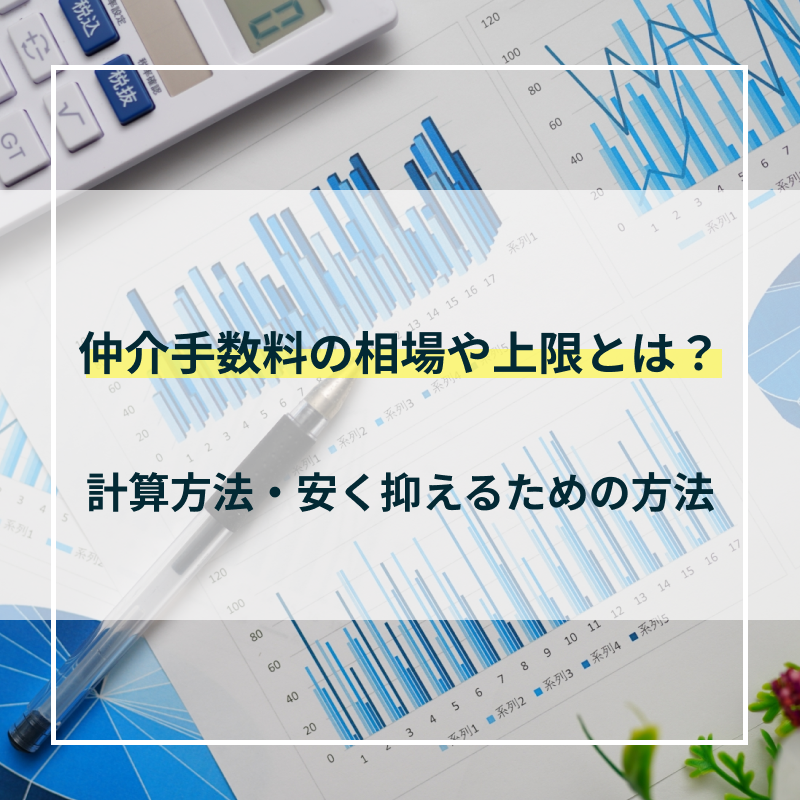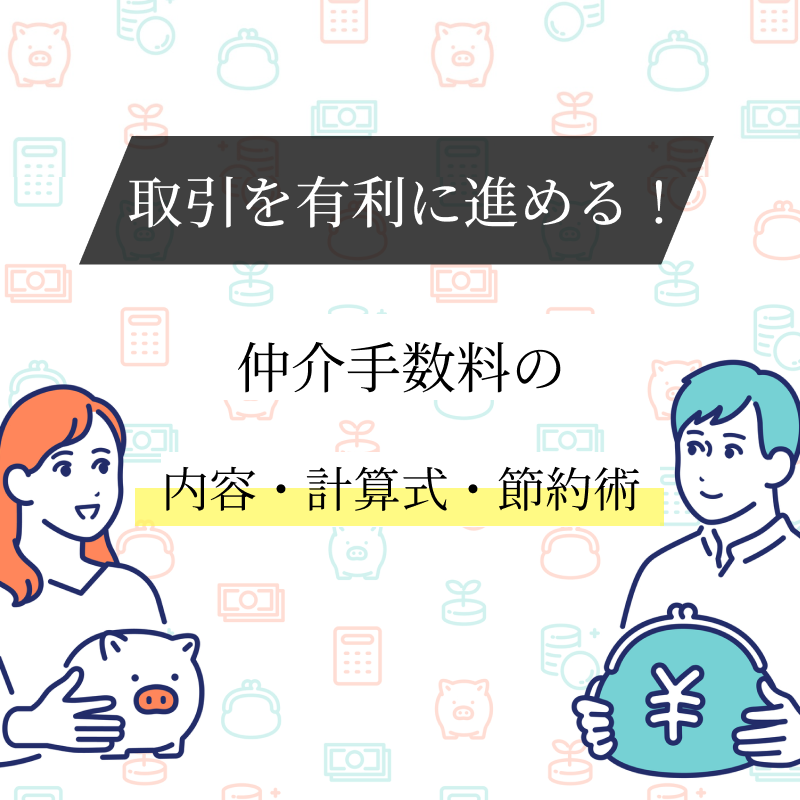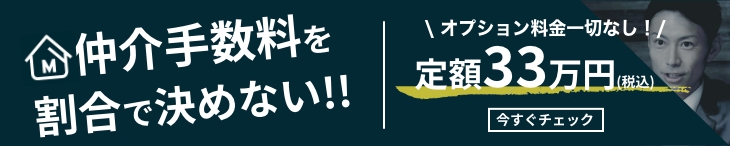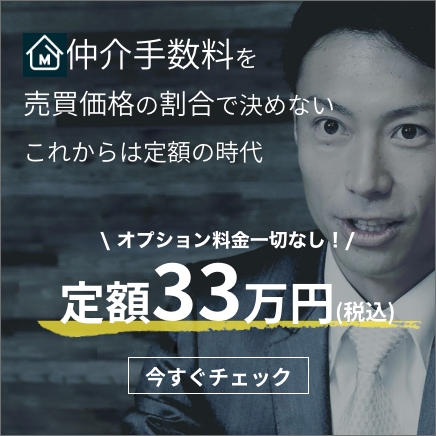
不動産売却時には税金がかかります。
特に売却による利益が大きければ、税金は数百万円にもなることもあります。
しかし、不動産売却時にはさまざまな税金の控除が用意されているので、控除を活用することで税金の支払いを抑えることも可能です。
不動産売却で必要な税金や計算方法、そして税金の支払いを抑えるための特別控除について詳しく解説していきます。
不動産売却でかかる税金
不動産売却時に支払いが必要な税金は次の4つです。
- 所得税(不動産売却で利益が出た場合)
- 住民税(不動産売却で利益が出た場合)
- 登録免許税
- 印紙税
所得税(不動産売却で利益が出た場合)
不動産の売却価額から取得にかかった経費を差し引きし、利益が出た際に課税される所得税には、譲渡所得税と復興特別支援税があります。
復興特別支援税は、東日本大震災の復興を目的として2037年まで義務付けられており、税率は2.1%です。
譲渡所得税は「売却する不動産を何年間所有したのか」によって税率が異なります。
譲渡所得税については、「不動産売却時の譲渡所得税」で詳しく解説します。
住民税(不動産売却で利益が出た場合)
不動産を売却して利益が出ると、翌年の住民税が上がります。
いつも納税している住民税とは別に、譲渡所得に応じて課税される住民税が加算されるからです。
住民税の納税方法や支払い時期については、「不動産売却時の納税方法と納税時期」で解説します。
登録免許税
不動産を売却した際、抵当権の抹消や住所変更の登記を行うため、登録免許税がかかります。
登録免許税は1つの不動産に対して1,000円かかります。
土地に対して1,000円、建物に対して1,000円かかるため、戸建て住宅であれば登録免許税は合計2,000円です。
参考元:法務局|登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続きのご案内)
印紙税
印紙税とは課税物件など、一定の文書に対して課税される税金です。
契約書や領収書などには印紙税がかかるので、それぞれの書類には収入印紙を貼付しなければなりません。
不動産売却の際には、不動産の売却金額に応じて次のような収入印紙代が発生します。
| 契約金額 | 印紙代 |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1千万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 |
例えば、自宅を3,000万円で売却するのであれば20,000円の収入印紙代が必要です。
印紙税は売買金額に応じて課税されるので、不動産売却によって利益が出なくても課税される税金であると理解しておきましょう。
不動産売却時の譲渡所得税
不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が課税されます。
この税金が不動産売却の際に最も大きなコストとなる税金です。
譲渡所得税は「売却する不動産を何年間所有したのか」によって次のように税率が異なります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 30.0% | 9.0% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.0% | 5.0% | 0.315% | 20.315% |
5年以内の短期譲渡所得は譲渡所得税の税率が39.63%と非常に高額です。
他方、5年超の長期譲渡所得の場合には税率は20.315%となります。
所有期間によって税率は大きく異なるので、所得を計算する際には必ず所有期間を確認し、「短期譲渡所得になるのか、長期譲渡所得になるのか」を把握しておきましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の計算式で算出します。
譲渡所得 = 不動産の売却価格 -(取得費+譲渡費用)
譲渡所得とは、不動産を取得した費用から減価償却費を控除した額より上回った分のことです。
ちなみに、不動産の取得費は次のように計算します。
- 土地:購入額
- 建物:建物購入価額-減価償却費相当額
土地については、土地を購入した価格が取得費用です。
1,000万円で購入した土地であれば1,000万円がそのまま取得費用となります。
建物は年数の経過とともに価値が下落していきます。
そのため、建物の取得価格から減価償却費を控除しなければなりません。
減価償却費の計算方法
一般的には減価償却費は定額法という計算方法で算出します。
定額法の計算式は次の通りです。
減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率とは建物の構造や耐用年数に応じてあらかじめ決められた価値を減価させるための割合のことです。
償却率は建物の構造や耐用年数に応じて次のようになっています。
| 建物の構造 | 耐用年数(非事業用) | 償却率(非事業用) | 耐用年数(事業用) | 償却率(事業用) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 33年 | 0.031% | 22年 | 0.046% |
| 木骨モルタル造 | 30年 | 0.034% | 20年 | 0.050% |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下) | 28年 | 0.036% | 19年 | 0.053% |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下) | 40年 | 0.025% | 27年 | 0.038% |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が4mm超) | 51年 | 0.020% | 34年 | 0.030% |
| 鉄筋・鉄骨コンクリート造 | 70年 | 0.015% | 47年 | 0.022% |
例えば購入価格3,000万円で築20年の木造住宅を売却する場合の減価償却費の計算は以下の通りです。
3,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年 = 1,674万円
建物の取得費 = 3,000万円 – 1,674万円 = 1,326万円となり、建物の売却価格が1,326万円を超えた場合には、超えた分が利益になります。
例えばこの建物が2,000万円で売却できた場合は、2,000万円-1,326万円= 674万円が利益で、674万円に対して譲渡所得税と住民税が課税されることになります。
まずは、購入時の建物の価格がいくらなのかということを売買契約書から確認しておきましょう。
不動産売却時の税金を節税する方法
不動産売却時にかかる税金を抑える方法はさまざま用意されています。
主な方法として次の5つの方法を考えることが可能です。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 居住用財産の所有期間が10年を超えた場合の軽減税率
- 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 未利用土地等の100万円特別控除
これらの方法を理解しておくことで、不動産売却時に発生する税金を大幅に抑えることができるでしょう。
不動産売却時の税金を節税する5つの方法について詳しく解説していきます。
税額の計算シミュレーション
では実際に、不動産売却によって譲渡所得が発生した場合、いくらの税金を支払う必要があるのか具体的に計算していきましょう。
次のケースの譲渡所得税を計算してみましょう。
ケース
- 建物購入価格:3,000万円
建物の構造:木造
経過年数:20年
土地購入価格:1,000万円
建物売却額:2,000万円
土地売却額:1,100万円
所有期間:5年超
建物減価償却費
3,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年 = 1,674万円
建物取得費
3,000万円 – 1,674万円 = 1,326万円
建物売却のよる利益
2,000万円 – 1,326万円 = 674万円
土地売却による利益
1,100万円 – 1,000万円 = 100万円
利益合計
674万円 + 100万円 = 774万円
譲渡所得税
774万円 × 20.315% = 1,572,381円
となります。
仮に利益が同じだった場合でも所有期間が5年以内であれば、譲渡所得税は次のようになります。
774万円 × 39.63% = 3,067,362円
全く同じ建物だとしても所有期間が5年以内なのか5年超なのかで、譲渡所得税は倍近く異なります。
不動産を売却する際には、とにかくまずは「所有期間は何年なのか」という点を確認しましょう。
なお、利益が出ないのであれば譲渡所得税はかかりませんので、所有期間を気にすることなく、売りやすいタイミングで売却してしまった方がよいでしょう。
譲渡損失が発生すれば翌年以降も節税できる
不動産売却によって譲渡所得が発生した場合には、譲渡所得税と住民税が課税されます。
そのため、売却によって損失が発生した場合には税金の支払いは不要です。
それだけでなく、翌年以降にも税金の支払いが軽減されることもあります。
不動産売却によって譲渡損失が発生した際の節税効果について解説していきます。
不動産売却時の納税方法と納税時期
不動産を売却した際にかかる税金は、納税方法と納税時期が以下のように異なります。
| 税金の種類 | 納税方法 | 納税時期 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 復興特別支援税 |
売却した翌年の確定申告後、税務署や銀行での現金支払い ・銀行振込・電子決済・クレジットカード決済・コンビニ決済・銀行口座からの自動引き落としのいずれかで納税 |
売却した翌年の確定申告期間中(2/16~3/15)申告時に 銀行口座からの自動引き落としを選択した場合は4月頃自動引き落とし |
| 住民税 | 給与所得者:6月以降の給与から天引き 給与所得者以外:6月以降に届く納付書で納税 (振り込み・電子決済・コンビニ決済など一括または4分割で選択可能) |
売却した翌年の確定申告後4分割で納付する場合 6月、8月、10月、1月末までに納税 |
| 登録免許税 | 法務局で手続きの場合:手続きの際現金で納付 3万円以下の場合:収入印紙を貼って納付も可能 |
抵当権の抹消など所有権の移転登記を申請したとき(まはたそれ以前) |
| 印紙税 | 売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税 | 売買契約を締結したとき |
不動産売却にかかる税金の注意点
不動産の売却で支払う税金での注意点は、以下の2点です。
- 確定申告を忘れるとペナルティが発生することもある
- 特例を活用しないと最大40%近い税金が発生することもある
確定申告を忘れるとペナルティが発生することもある
不動産売却で利益が発生したにもかかわらず確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」という追徴課税が課される可能性があり、注意が必要です。
原則として納付すべき税額に対して、以下のように税金が加算されます。
| 課税の基準 | 課税割合 |
|---|---|
| 50万円まで | 15% |
| 50万円を超え300万円以下の部分 | 20% |
| 300万円を超える部分 | 30% |
引用元:財務省|加算税の概要
また納税期限を過ぎた日数に応じて、2カ月以内の場合は納税金額の7.3%、2カ月を過ぎると14.6%の延滞税も請求されます。
引用元:国税庁|延滞税の計算方法
特例を活用しないと最大40%近い税金が発生することもある
不動産の売買にかかる譲渡所得税の税率は最大で39.63%です。
例えば不動産の売却で1,000万円の利益が出れば、税金の支払いだけで390万円以上になることもあります。
不動産売却の際に、特例の活用など節税について理解しないことは非常にリスクの高い行為だとしっかりと認識しておきましょう。
オススメ記事
不動産売買の仲介手数料は消費税あり?売却費用を抑えてスムーズに取引するコツ
不動産売却のファーストステップとなる不動産の査定をどこに依頼すればいいのか?一括査定をしてくれるサービスがいくつかあります。査定は売却において重要なポイントなので、信頼できる不動産会社にお願いしたいですよね。そこで、不動産一括査定サービスを提携社数や対応エリアなど項目に沿って、業界の専門家が解説します。

まとめ
住宅を売却する際にはさまざまな費用や税金がかかりますが、最も大きな負担は売却益に対して課税される譲渡所得税です。
まずは、譲渡所得がいくらになるのかを計算できるようになりましょう。
また、所有期間が5年以内なのか、5年超なのかによって税率は大きく異なるので、売却活動を始める前には必ず短期譲渡所得になるのか長期譲渡所得になるのかを確認しておきましょう。
その他、不動産の売却にはさまざまな特別控除があるので、「どんな制度が利用できるのか」という点をしっかりと確認しておいてください。